宅地建物取引士、FP2級保有 不動産・建設会社の土地有効活用のコンサルティング営業を6年担当。現在は不動産や建設業界の知見を活かした不動産や金融ジャンルのライターとして活動しています。
「中古住宅の購入は何から始めればいいの?」「どれぐらいの期間がかかるの?」という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、
- 中古住宅購入の流れ
- 中古住宅購入にかかる期間の目安
- 中古住宅購入で活用できる補助金と税制優遇
- 買ってはいけない中古住宅を見抜くためのポイント
を紹介します。
中古住宅購入を成功させるコツは、物件探しから引き渡しまでの全体の流れと、各ステップでのポイントを事前に正しく理解しておくことです。この記事を読めば、中古住宅購入の全体像が明確になり、自信を持って理想の住まい探しを始められるでしょう。
目次
中古住宅購入の流れ全8ステップ
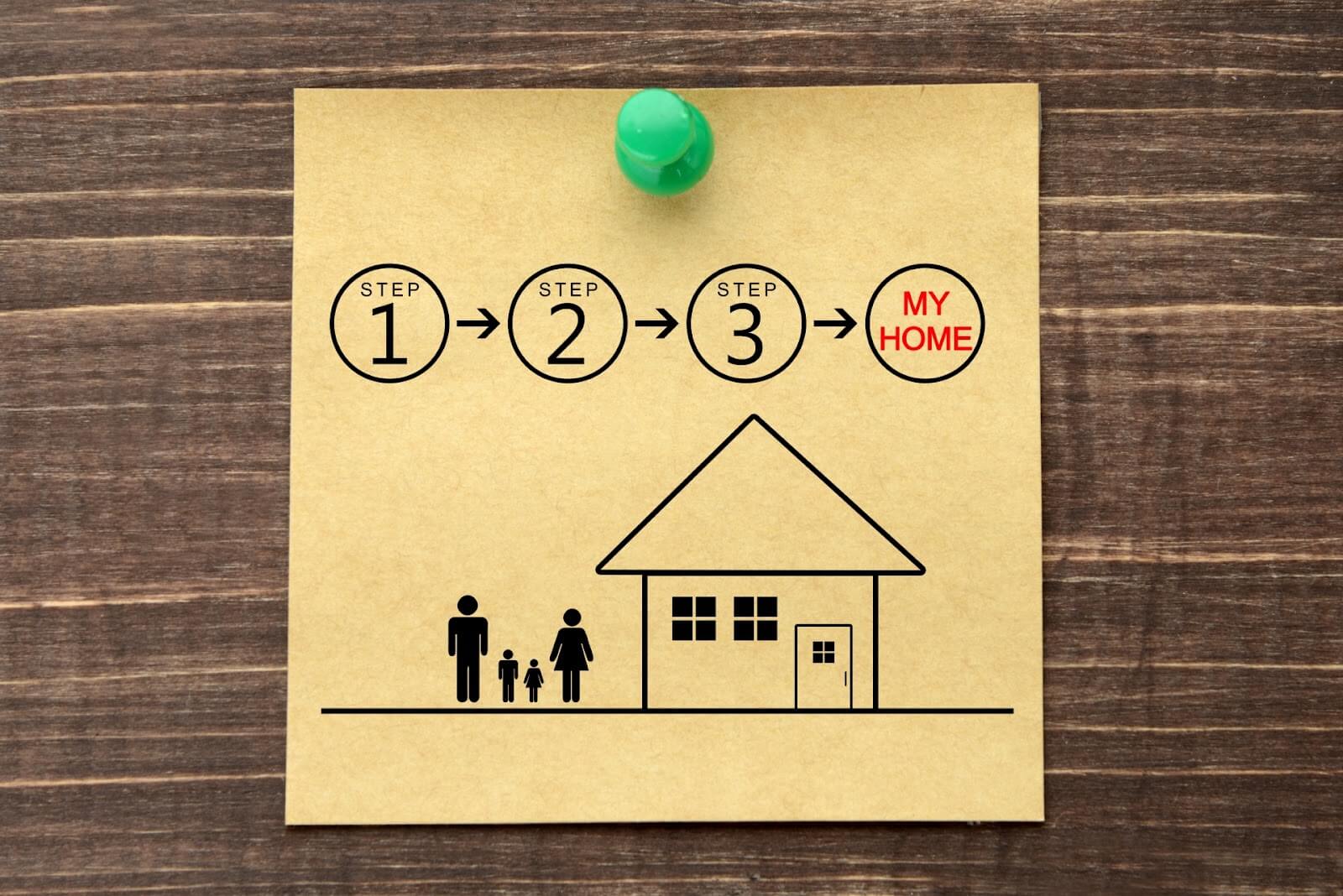
中古住宅の購入は、人生における大きな決断の一つです。そのため、どのような流れで進むのかを事前に把握し、計画的に準備を進めることが重要です。全体像を理解することで、各ステップで何をすべきかが明確になり、不安なく手続きを進められます。理想の住まいを見つける準備から、実際に物件の鍵を受け取るまでの全8ステップを、それぞれ掘り下げて解説します。
理想の住まいを見つけるための準備を始める
最初のステップは、理想の住まいに関する希望条件を整理することです。条件が曖昧なままでは、数多くの物件の中から自分に合ったものを見つけ出すことが困難になります。まずは「絶対に譲れない条件」と「できれば満たしたい条件」に分けてリストアップすると、思考が整理しやすくなります。
例えば、以下のような条件をリストアップしてみましょう。
- 駅からの距離
- 最低限必要な部屋数
- 通勤時間
- バルコニーの方角
- 学区
- 築年数
また、将来の家族構成の変化やライフプランまで見据えて条件を設定することで、長く快適に暮らせる住まいを選択可能です。子どもの成長による部屋数の変化、親との同居の可能性、テレワークの導入による働き方の変化などを具体的に想像してみましょう。
無理のない資金計画を立てて予算を決める
理想の条件が固まったら、無理のない資金計画を立てて購入予算を明確にしましょう。予算を決めずに物件探しを始めると、将来の家計を圧迫する買い物になりかねません。
中古住宅の購入には、物件価格とは別に、以下のような費用が発生します。
- 仲介手数料
- 登記費用
- 不動産取得税などの各種税金
- ローン保証料
- 火災保険料
中古住宅を購入する際は、物件価格の6%から10%ほどの諸費用も必要になるのが一般的です。ご自身の年収から毎月無理なく返済できる額を計算し、住宅ローンの事前審査で借入可能額を把握しておけば、安心して物件探しを進められるでしょう。
その際に参考になるのが「返済負担率」です。返済負担率とは、年収に占める年間のローン返済額の割合を指し、一般的には20%から25%が健全な目安とされています。
さらに、住宅ローンの事前審査を受けておくことで、実際にいくら借りられるのかを把握でき、購入できる物件の目安が明確になります。これにより、安心して物件探しを進められるだけではなく、不動産会社や売主からの信頼も得やすくなるでしょう。
中古住宅の購入予算や資金計画で悩んでいる方は、JR神戸駅から徒歩すぐの「HDC神戸」で各リフォーム会社の担当者に補助金や資金計画を直接相談しましょう。複数社のプランを一度に比較でき予算と制度の悩みを解消できます。
信頼できる不動産会社を選んで物件を探す
資金計画の次に行うのは、理想の住まい探しを支援してくれる信頼できる不動産会社選びです。不動産会社は、専門的な知識で物件探しを手伝い、複雑な手続きを円滑に進める心強いパートナーです。
不動産会社には、全国的な情報網と実績を持つ大手と、特定のエリアの未公開情報や地域特性に精通した地域密着型の会社があります。それぞれの長所と短所を比較検討し、ご自身の希望に合った会社を選ぶことが重要です。
また、担当者との相性も無視できません。ご自身の要望を真摯に聞き、プロとして的確な提案をしてくれるか、質問に対して誠実に回答してくれるかを見極めましょう。会社の信頼性を客観的に確認するためには、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで免許番号や過去の行政処分歴を調べることも有効な手段です。
建設業者・宅建業者等企業情報検索システムでは、以下のような項目を調査できます。
- 宅建業の免許番号
- 営業所所在地・商号
- 過去の行政処分歴
検索にあたっては、以下のポイントを意識して確認しましょう。
- 免許の更新状況:免許が現在も有効かを必ず確認しましょう。有効期限が切れている場合、無許可営業のリスクがあります。
- 行政処分歴の有無と内容:過去に行政処分を受けていないか、受けていた場合はその内容にも目を通しておくことが大切です。特に「業務停止命令」や「免許取消処分」がある場合は注意が必要です。
- 営業年数や支店の有無:長年営業を続けているか、複数の支店を展開しているかも信頼性の判断材料になります。地域での実績や対応力の高さがうかがえる場合があります。
このように、公的な情報をもとに事前に確認しておくことで、悪質な業者とのトラブルを回避し、安心して住まい探しを進めることができます。
物件内覧で確認すべきチェックリストを準備する
気になる物件が見つかったら、物件の内覧に進みます。その際は、事前に確認項目をまとめたチェックリストを準備して臨むことが後悔しないためのポイントです。現地では気持ちが高ぶり、部屋のきれいさや広さばかりに目が行きがちで、重要な点の確認を怠る可能性があります。
室内の状態はもちろん、日当たりや風通し、水回りの水圧や排水状況、収納の容量、コンセントの位置と数などを細かく確認しましょう。マンションの場合は、エントランスや廊下、ゴミ置き場といった共用部の管理状態も、管理組合の機能度を測る上で重要な指標です。
さらに、平日と休日、昼と夜など、異なる時間帯に複数回訪れると、周辺の交通量や騒音、街の雰囲気の変化を体感でき、住んでからの生活を具体的に想像できます。
購入申込と売主への条件交渉
購入したい物件が決まったら、購入申込書を不動産会社へ提出し、売主に購入の意思を正式に伝えます。一般的に「買付証明書」と呼ばれるこの書類が、価格や諸条件に関する交渉を進めるうえでの第一歩です。
価格だけではなく、物件の引き渡し時期やエアコン、照明器具、カーテンといった設備の有無に関する条件も交渉対象になります。内覧や住宅診断で修繕が必要な箇所が見つかった場合は、その修繕見積もりなどを客観的な根拠として提示することで、価格交渉が円滑に進みやすくなります。
希望する条件はすべて明確に、かつ書面で伝えることが後のトラブルを避けるために重要です。不動産会社の担当者と戦略を練りながら、双方が納得のいく条件で契約を進めましょう。
不動産売買契約と重要事項説明
売主との間で条件の合意に至れば、不動産売買契約を締結します。これは法的な効力を持つ重要な契約であり、内容を十分に理解した上で進める必要があります。契約前には、宅地建物取引士から物件の権利関係や法的な制限などが記載された「重要事項説明」を必ず受けてください。
重要事項説明では、以下のような専門的かつ多岐にわたる情報が提示されます。
- 登記情報(所有者・抵当権の有無など)
- 都市計画法による制限(用途地域や建ぺい率など)
- 前面道路の状況(幅員、接道義務など)
- ハザードマップの内容(洪水・土砂災害リスクの有無)
- 手付金の額や扱い
- 住宅ローン特約の有無
- 契約後に欠陥が見つかった場合の売主の責任(契約不適合責任)
これらの項目は一つひとつ丁寧に確認し、少しでも疑問があればその場で遠慮なく質問することが大切です。なお、以下のような専門用語についても事前に理解しておくと安心です。
- 契約不適合責任:引き渡された物件が契約内容と異なる状態だった場合に、売主が負う責任のこと。
- 住宅ローン特約:ローン審査に通らなかった場合に、契約を無条件で解除できる特別な取り決め。
重要事項説明は、契約後のトラブルを防ぐための重要な工程です。専門用語が多く不安に感じるかもしれませんが、納得いくまで確認する姿勢を持ちましょう。
住宅ローンの本審査と金銭消費貸借契約
売買契約が無事に完了したら、速やかに住宅ローンの本審査を申し込みましょう。事前審査に通過していても、売買契約書などの正式な書類を提出して行われる本審査で、最終的な承認が必要です。
本審査では、申込者の年収や勤務先、信用情報といった属性情報に加えて、購入物件の担保価値も評価されます。本審査の承認が下りたら、次はお金を借りる金融機関との間で金銭消費貸借契約を結びます。
金銭消費貸借契約は、金融機関から融資を受ける際に結ぶ契約です。金銭消費貸借契約をする際には、団体信用生命保険への加入が一般的ですが、健康状態は正確に告知することが重要です。
団体信用生命保険とは、ローン契約者に万が一のことがあった際に、保険金で残債が支払われる保険を指します。虚偽の告知をすると、いざという時に保険金が支払われない可能性があるため注意が必要です。
残代金の決済と物件の引き渡し
すべての手続きの最終段階が、残代金の決済と物件の引き渡しです。一般的には、買主、売主、不動産会社の担当者、登記手続きを行う司法書士が金融機関の応接室などに集まり、平日の午前中に行われることが多いです。
住宅ローンが実行されて売主の口座へ残代金が送金され、着金が確認されると、同時に司法書士が所有権を買主へ変更する登記手続きを法務局に申請します。固定資産税や都市計画税、マンションの管理費などの日割り精算、不動産会社への仲介手数料の支払いなどもこの時に済ませます。
すべての手続きが完了し、最後に売主から物件の鍵を受け取れば、名実ともに物件がご自身のものとなり、新しい生活の始まりです。
中古住宅購入にかかる期間の目安

中古住宅の購入を考え始めたら、実際に住み始めるまでに必要な期間を把握しておくことが大切です。全体のスケジュール感を理解しておけば、現在の住まいの退去手続きや引越しの準備などを計画的に進められます。先述したとおり、購入までには多くステップがあり、それぞれに時間を要するため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。
全体で3ヶ月~6ヶ月が一般的な期間
中古住宅の購入では、検討を開始してから入居するまで、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。この期間は、物件探しにかける時間、住宅ローンの手続きの進捗、売主の住み替えの都合など、さまざまな要因によって変動します。
希望条件に合う物件がすぐに見つかり、手続きが順調に進めば3ヶ月程度で完了することもあります。しかし、交渉が長引いたり、リフォームを伴ったりする場合は半年以上かかることも想定し、余裕を持って計画を立てることが重要です。
各ステップごとの期間の目安を把握する
全体の期間を把握するために、各ステップのおおよその所要時間を知っておきましょう。希望の物件を探し始めてから購入の申し込み、そして売買契約を結ぶまでが、個人差が出る期間で、およそ1ヶ月から3ヶ月です。
次に、売買契約後に申し込む住宅ローンの本審査には、金融機関の審査状況にもよりますが、結果が出るまで2週間から4週間ほどかかります。無事にローン審査の承認が下りてから、金融機関との金銭消費貸借契約を経て、残代金の決済と物件の引き渡しが完了するまでには、さらに1ヶ月から2ヶ月程度を見込んでおくと良いでしょう。
新築住宅購入との期間の違い
中古住宅と新築住宅では、購入にかかる期間に大きな違いがあります。新築の場合、まだ建物が完成していない未完成物件であれば、契約から引き渡しまで数ヶ月から1年以上かかることもあります。
一方、中古住宅はすでに建物が存在するため、契約から引き渡しまでの期間が比較的短く、条件が合えば早期に入居できる点が魅力です。ただし、中古住宅特有のステップとして、物件の状態を詳しく確認するための住宅診断の実施や、売主の退去を待つ期間が必要になる場合があります。
大規模なリフォームを計画している場合は、設計や工事の期間が加わるため、新築と同じくらいの期間がかかることも想定しておきましょう。
期間を短縮するためのポイント
中古住宅の購入期間を短縮したい場合は、いくつかのポイントを意識することで、効率よく手続きを進めることができます。特に、以下の点を押さえておくとスムーズです。
- 住宅ローンの事前審査は早めに済ませる:物件探しを始める段階で事前審査を受けておくと、予算の上限が明確になり、気に入った物件が見つかった際にすぐに購入申込ができます。
- 複数の金融機関に同時申し込みして比較する:事前審査を複数行うことで、金利や条件の良い金融機関を選びやすくなり、意思決定も早まります。
- 本審査に必要な書類をあらかじめ準備する:住民票・印鑑証明書・課税証明書などは取得に時間がかかることもあるため、事前に用意しておくと審査や契約がスムーズに進みます。
- リフォーム予定がある場合は並行して進める:購入後にリフォームを予定している場合は、物件探しと同時にリフォーム会社への相談も進めておくと、引き渡し後の工事もスムーズにスタートできます。
これらの準備をあらかじめ行っておくことで、購入から入居までの期間を大幅に短縮できるでしょう。
中古住宅購入で活用できる補助金と税制優遇

中古住宅を購入する際には、経済的な負担を軽減する制度が用意されています。これらを上手に活用することで、大きなメリットを受けられる可能性があります。国や自治体が実施している補助金制度や、税金の負担を軽くする優遇措置など、事前にどのような制度があるのかを理解し、ご自身が利用できるものを漏れなく活用しましょう。
利用できる補助金制度と申請のタイミング
中古住宅の購入やリフォームでは、国や自治体が提供する補助金制度を利用できる場合があります。これは、良質な住宅ストックの形成や省エネ化の促進などを目的とした制度で、返済不要の給付金が受けられるため、積極的に活用を検討しましょう。
例えば「子育てグリーン住宅支援事業」は、子育て世帯や若者夫婦世帯が特定の省エネ改修などを行った場合に補助が受けられます。これらの補助金は申請期間や対象となる住宅・工事の条件、予算上限が厳格に定められており、予算に達し次第終了となるため、不動産会社やリフォーム会社に相談しながら早めに情報を確認し、計画的に申請することが重要です。
住宅ローン控除など税金の優遇制度
住宅ローンを利用して中古住宅を購入した場合、年末のローン残高に応じて所得税が還付される「住宅ローン控除」という税制優遇制度があります。住宅ローン控除とは、年末のローン残高に準じて一定期間、所得税や住民税が還付される制度です。
住宅ローン控除を最大限に活用するためには、購入する中古住宅が現行の耐震基準を満たしている必要があります。築年数が古い物件でも、耐震基準適合証明書などを取得できれば適用の対象です。
また、住宅を取得した際に一度だけ課される不動産取得税や、登記手続きに必要な登録免許税についても、特定の条件を満たす良質な中古住宅に対しては税率が軽減される措置が設けられています。
リフォーム一体型ローンの活用
中古住宅を購入して自分好みにリフォームしたい方には「リフォーム一体型ローン」の活用が有効です。これは、物件の購入費用とリフォーム費用を一つの住宅ローンとして低金利で借り入れできる金融商品です。
購入資金とリフォーム資金を別々にローンで組むよりも金利を抑えられるだけではなく、窓口が一本化されるため手続きが一度で済むという大きなメリットがあります。ただし、金融機関によって融資の条件や審査基準、対象となるリフォーム工事の範囲が異なります。
リフォームの見積書を取得する必要があるなど、独自の段取りも求められるため、物件探しと並行して複数の金融機関へ相談し、ご自身に合ったプランを見つけておくことが大切です。
買ってはいけない中古住宅を見抜くためのポイント

数多くの中古住宅の中には、購入後に思わぬトラブルや多額の出費につながる可能性のある物件もあります。契約前にリスクのある物件を見抜くための知識を身につけておくことが重要です。建物の安全性や将来の資産価値、法律上の制約など、事前に確認すべきポイントを見ていきましょう。
旧耐震基準の物件は慎重に検討する
建物の耐震性は、命に関わる重要な項目です。特に、1981年5月31日以前の建築確認で適用された「旧耐震基準」の物件は、震度5強程度の揺れで倒壊しないことを基準としており、現在の耐震基準を満たしていない可能性があるため、慎重な確認が求められます。
現在の新耐震基準は、震度6強から7の地震でも倒壊しないことを目指している基準値です。旧耐震基準の物件は、地震に対する安全性が低いだけではなく、住宅ローン控除などの税制優遇が受けられない場合や、資産価値が低く評価されるといった側面も持ちます。耐震診断の有無や必要な補強工事が完了しているか、またその費用はいくらかかるのかを必ず確認することが不可欠です。
過去の修繕履歴が不明な物件は避ける
建物の維持管理状態を把握する上で、過去の修繕履歴は重要な情報源です。修繕履歴が不明な物件は、適切なメンテナンスが行われてこなかった可能性があり、購入後に雨漏りや給排水管の故障など、想定外の修繕費用が発生するリスクを抱えます。
マンションの場合は、管理組合が保管する長期修繕計画や大規模修繕の実施記録を取り寄せ、計画通りに修繕が行われているか、修繕積立金は十分に確保されているかを確認しましょう。
戸建ての場合は、売主に対して過去の外壁塗装や屋根のメンテナンス、シロアリ対策の履歴などを具体的に確認し、書面で保管されている資料があれば提出してもらいましょう。これが建物の健康状態を把握する上で不可欠です。
土地の権利や法律上の制限を必ず確認する
見落としがちですが、建物が建つ土地の権利関係や法律上の制限の確認は必須です。例えば、接している道路の幅が建築基準法上の規定に満たないなどの理由で、既存の建物を取り壊すと建て替えができない「再建築不可物件」があります。再建築不可物件とは、現在の法律では同じ規模の建物を建て替えられない物件のことで、資産価値が低く、売却も困難です。
また、土地の権利が「借地権」の物件は、毎月の地代や将来の更新料負担が発生します。借地権とは、地主から土地を借りて建物を使用する権利のことです。重要事項説明の際にこれらの権利関係や法規制の内容をよく確認し、将来の建て替えや増築が計画通りに行えるかを必ず確認しましょう。
まとめ|中古住宅購入の流れを理解して理想の住まいを手に入れよう

中古住宅の購入は、多くの人にとって大きな買い物です。物件探しから引き渡しまでの全体の流れを正しく理解し、一つひとつのステップを着実に進めていくことが、後悔のない選択につながります。
資金計画や物件の内覧、契約手続きなどやるべきことは多岐にわたりますが、事前に知識を身につけておけば、不安を解消し、自信を持って判断を下せます。この記事で解説した詳細なステップと注意点を参考に、ご自身にとって最高の住まいを見つけてください。
なお、「購入予算にどれくらいかけていいのか」「補助金はどれが使えるのか」といったお金まわりの不安を抱えている方も多いかもしれません。そうした場合は、専門家に直接相談して具体的なプランを明確にするのがおすすめです。
中古住宅の購入予算や補助金の活用で悩んでいる方は、JR神戸駅から徒歩すぐの「HDC神戸」で各リフォーム会社の担当者に補助金や資金計画を直接相談できます。複数社のプランを一度に比較でき予算と制度の悩みを解消できるでしょう。お近くの方はぜひ足を運んでみてください。
こちらの記事もお役立てください






 鶏肉の茹で時間は10分必要?安全に美味しく仕上がる茹で時間や方法はこちら!
鶏肉の茹で時間は10分必要?安全に美味しく仕上がる茹で時間や方法はこちら!  着払いで荷物を送るにはどの方法がお得!?配送業者別に料金や送り方を徹底比較
着払いで荷物を送るにはどの方法がお得!?配送業者別に料金や送り方を徹底比較  簡単ウエスト直し術|自分で簡単にウエストのお直しができる裏ワザ
簡単ウエスト直し術|自分で簡単にウエストのお直しができる裏ワザ 





