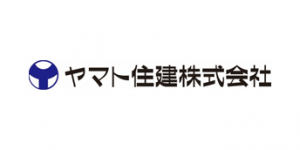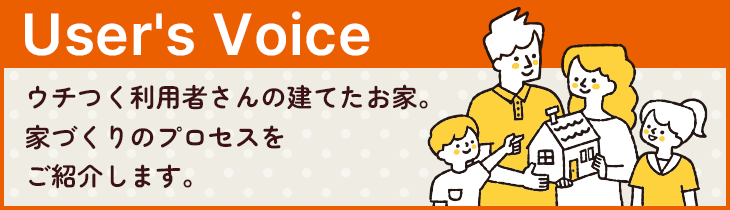日影規制有の土地を徹底解説!調べ方から緩和措置まで後悔しない選び方を紹介

念願のマイホーム、理想の間取りやデザインを思い描く時間はとても楽しいものですよね。しかし、その計画をスムーズに進める上で日影規制というルールは避けて通れません。言葉は聞いたことがあるけど、なんだか難しそうと感じていませんか?実は、この規制を知らないまま土地を選んでしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
この記事では、日影規制の基本から簡単な調べ方、そして対策までを解説します。読み終える頃には不安が解消され、自信を持って理想の家づくりに向けた土地選びができるようになっているはずです。
日影規制について

理想の家づくりを考える上で、デザインや間取りと同じくらい大切なのが日影規制というルールです。この規制は、隣地との日当たりを確保し、お互いが快適に暮らすために定められています。一見、難しそうに聞こえるかもしれませんが、基本的な知識を持つことで、土地選びの失敗を防ぎ、計画をスムーズに進めることができます。まずは、日影規制がどのようなもので、家づくりにどう影響するのかを一緒に見ていきましょう。
日影規制とは
日影規制とは、新たに建築する建物が隣接する土地の日照を長時間妨げないように、建築基準法で定められたルールのことです。この規制によって、住宅が密集する地域でも互いの日当たりが確保され、良好な住環境が維持されています。
基準となるのは、一年で太陽が最も低くなり影が長くなる冬至の日です。この日に、隣の土地へ一定時間以上の日影ができないよう、建物の高さや形状が制限されます。周辺環境との調和を図り、快適な暮らしを守るための重要な決まりといえるでしょう。
日影規制の条件
日影規制は、全ての土地や建物に一律で適用されるわけではなく、特定の条件を満たす場合にのみ対象になります。主に、居住することを目的とした住居系の用途地域で適用され、商業地域や工業地域では原則として対象外です。
また、規制の対象となる建物は、軒の高さが7メートルを超える、もしくは地下を除く3階建て以上のものです。影を測定する高さは地面からではなく、一般的な住宅の1階の窓の高さを想定した、平均地盤面から4メートルまたは6.5メートルの位置で計算されるのが特徴です。
日影規制が家づくりに与える影響
日影規制は、これから建てる家の計画に直接的な影響を及ぼす可能性があります。規制対象の土地では、定められた時間内に影が収まるよう、建物の高さや形状を工夫する必要があるためです。
たとえば、開放的な高い天井や3階建ての住まいを希望していても、規制をクリアするために階数を減らしたり、屋根の形状を斜めにしたりといった設計変更が求められるケースがあります。したがって、土地を購入する前の段階で日影規制の有無や内容をきちんと把握しておくことが、後悔しない家づくりのために欠かせません。
日影規制を調べる方法

自分の土地や購入を検討している土地に日影規制があるかどうかは、どうやって確認すれば良いのでしょうか。専門知識がないと難しそうに感じるかもしれませんが、心配いりません。自分で手軽に調べられる方法から、専門家に依頼する確実な方法まで、いくつかの手段があります。
ネットで都市計画図をチェックする
まず、パソコンやスマートフォンを使い、手軽に調べる方法があります。ほとんどの自治体は、公式Webサイト上で都市計画図を公開しています。Googleなどの検索エンジンで「〇〇市 都市計画図」のように入力して探すと良いでしょう。
この地図では、土地の用途が色分けで示されていて、対象の土地がどの用途地域に指定されているかを確認できます。日影規制は主に住居系の用途地域で適用されるため、用途地域を把握するだけでも、規制対象となる可能性を大まかに判断できます。
市役所で正確な情報を聞く
インターネットでの確認は手軽ですが、より正確で詳しい情報を得るには、市役所や区役所の窓口で直接確認するのが確実です。建築関連の相談を受け付けている建築指導課や都市計画課といった部署で確認できます。
その際、調べたい土地の地番がわかる書類、たとえば登記簿謄本や公図の写しなどを持参すると手続きが円滑に進みます。窓口で土地の日影規制について尋ねれば、規制があるかどうかや、規制時間、測定面の高さといった具体的な内容を知ることが可能です。
プロに調査を任せる
最も確実で安心な方法は、不動産会社や住宅メーカーといった、家づくりの専門家に調査を依頼することです。日影規制の解釈は複雑で、他の法律も関係するため、専門知識がなければ正確な判断は難しい場合があります。
特に土地の購入を検討している段階では、契約前に不動産会社を通して調査してもらうのが一般的です。調査内容は重要事項説明書に書かれ、宅地建物取引士から説明を受けます。購入後のトラブルを避け、希望の家が建てられるか確かめるためにも、専門家による調査は欠かせません。
日影規制の時間と測定基準
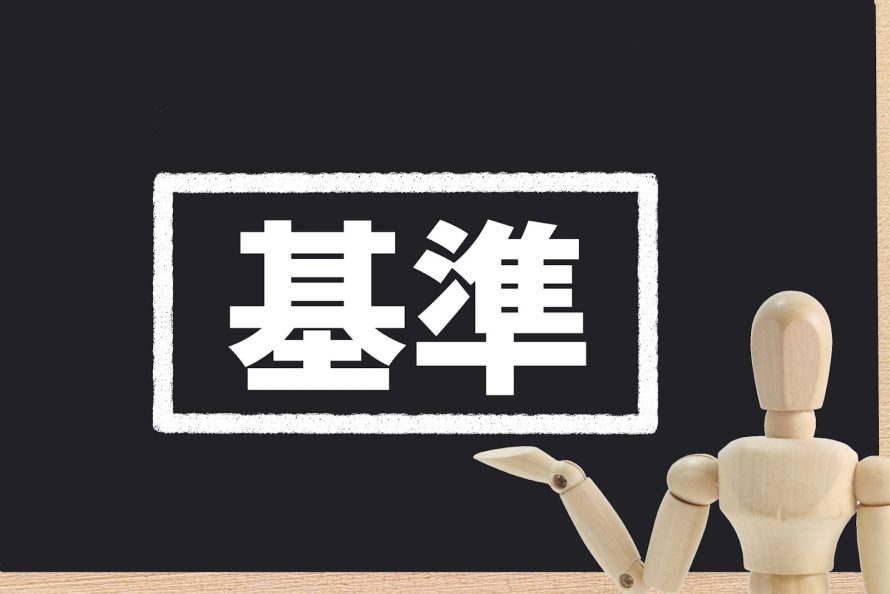
日影規制について調べていると5-3h/4mといった記号のような表記を目にすることがあります。この暗号のような表記を読み解くことで、自分の土地に課せられたルールの具体的な内容がわかります。さらに、影を測定する高さの基準や、影の動きをシミュレーションする日影図について知ることで、より深く規制を理解し、家づくりにいかすことができるでしょう。
規制時間の表記を読み解く
日影規制の具体的な内容は5-3h/4mのような形で示されます。これは、敷地境界線から5メートル以内の範囲は1日に5時間まで、5メートルを超え10メートル以内の範囲は3時間まで日影になっても良い、という許容時間を表しています。
末尾の/4mは、影を測定する面の高さが地面から4メートルという意味です。この規制の種類はひとつではなく、自治体や用途地域ごとに複数の選択肢から指定されます。建物の密集度や地域の特性に応じて、互いの日当たりを適切に確保できるよう、最適なルールが設定されています。
測定面の高さで何がわかるか
日影規制の表記にある測定面の高さは、近隣住宅のどの部分の日当たりを守るべきかを示す重要な基準です。たとえば測定面が4メートルの場合、これは一般的な2階建て住宅の1階部分の日当たりを守ることを想定しています。
一方、3階建て以上の建物が多い地域では、測定面が6.5メートルに設定されることがあります。これは2階部分の日当たりを確保するための基準です。一般的に、測定面が高く設定されているほど地面に落ちる影は測定ラインに届きにくくなるため、規制としては緩やかになる傾向にあります。
日影図で影の動きを見える化する
計画中の建物が日影規制をクリアできるか、最終的に確認するのが日影図です。これは、設計した建物が冬至の日の時間ごとにどのような影を作るか、シミュレーションした専門的な図面のことです。
特定時刻の影の形を示す時刻日影図や、同じ時間だけ影になる範囲を線で結んだ等時間日影図など、いくつかの種類が存在します。建物の影の動きは複雑なため、家を設計する際は建築士などの専門家がこの日影図を作成し、法規制をきちんと満たしているかを確認します。
日影規制をクリアする緩和措置と対策

日影規制があると知ると「もしかして希望通りの家は建てられないのでは」と不安に思うかもしれません。しかし、諦めるのはまだ早いです。建築基準法には、厳しい規制を乗り越えるための緩和措置や、建物の設計を工夫する方法が用意されています。ここでは、日影規制を乗り越えるための具体的な対策を紹介します。
立地条件をふまえて緩和措置を受ける
全ての土地で同じように厳しい規制がかかるわけではなく、特定の立地条件を満たす場合は規制が緩和されることがあります。たとえば、敷地が道路や川、公園などに接している場合、日当たりへの影響が少ないと判断されるためです。
また、隣の土地との間に高低差がある場合も、影の影響が通常とは違うため、特別な緩和措置が設けられています。ただし、これらの緩和規定が適用できるかどうか専門的な知識なしに判断するのは難しいです。自己判断はせず、必ず建築士などの専門家に相談して適用可能かを確認することが重要になります。
天空率を活用して高さ制限を回避する
日影規制をクリアする有効な手段として天空率という制度があります。これは、建物の周囲の特定のポイントから空を見上げたとき、空がどれくらいの割合で見えるかという開放感を数値で評価するものです。
この天空率が基準値を満たしていれば、たとえ建物が日影規制のルールを超えていても、規制の適用が免除されます。この方法の大きなメリットは、日影規制だけではなく、建物の高さを制限する他の斜線制限も同時にクリアできる可能性がある点です。天空率の活用で、設計の自由度は格段に高まります。
建物の設計を工夫して規制をクリアする
緩和措置や天空率の活用に加えて、建物の設計そのものを工夫することでも日影規制に対応できます。これは、影の形や長さを制御するために、建物の配置や形状を最適化する方法です。
たとえば、建物を敷地の北側に寄せて配置したり、北側の屋根の形を低く設計したりするだけでも、南側の隣地に落ちる影は短くなります。また、ひとつの大きな建物ではなく、二つの小さな建物に分ける分棟化という手法で影の影響を減らすケースもあります。これらの対策は高度な専門知識が必要なため、設計の初期段階で建築士と十分に話し合うことが大切です。
日影規制がある土地を購入するときの注意点

日影規制のある土地は、一見すると制約が多くて不安に感じるかもしれません。しかし、購入前にいくつかのポイントをしっかりと押さえておけば、後悔するリスクを大幅に減らすことができます。ここでは、日影規制のある土地を安心して購入するために、契約前に必ずチェックしておきたい3つの注意点について解説します。
重要事項説明で必ず確認しておく
土地の売買契約を結ぶ前には、宅地建物取引士から重要事項説明を受けることが法律で義務付けられています。これは、土地の法的な制限などを書面に基づいて解説する重要な機会です。
日影規制のあるかどうかや、その具体的な内容である規制時間、測定面の高さなども必ず説明される項目です。説明の中でわからない言葉や疑問点があれば、その場で質問して疑問や不安を解消することが大切になります。将来の規制変更の可能性も含め、全てに納得した上で契約に進む姿勢が、後のトラブルを防ぐことになるでしょう。
周辺環境を自分の目で確かめる
書類や地図での確認とあわせて、必ず現地を訪れて周辺環境を自分の目で確かめることが重要です。書類だけでは読み取れない、細かい現実の状況を把握できます。
たとえば、隣接する土地の状況や、南側に現在空き地がある場合に将来高い建物が建つ可能性などを考えます。また、季節や時間帯による日当たりの変化を実感するため、できれば晴れた日の午前と午後の両方で現地を訪れるのがおすすめです。実際の光や風を感じることで、そこでの暮らしをより具体的にイメージできるでしょう。
専門家に事前調査を依頼する
最終的な安心を得るには、土地の購入を決める前に、建築のプロである建築士に詳細な調査を依頼するのが確実な方法です。専門家は、その土地の日影規制や他の法規制を全て考えた上で、希望する家の計画が実現可能かを具体的に検証します。
この段階を踏むことで「契約したのに、思ったような家が建てられなかった」という事態を避けられます。費用は発生しますが、これは理想の家づくりを成功させるための重要な投資といえるでしょう。購入後のトラブルを防ぐためにも、万全の準備を整えることが大切です。
まとめ|日影規制を理解して理想の家づくりを実現しよう

この記事では、日影規制の基本から調べ方、対策までを解説しました。日影規制は、周囲の住環境に配慮しながら家を建てるための重要なルールです。理想の住まいを実現するには、土地の特性や法規制を事前に理解し、それに対応できる家づくりの進め方を考えることが欠かせません。まずは気になる土地の用途地域や規制状況を自治体のWebサイトで確認し、次のステップとして不動産会社や建築士などの専門家に相談してみましょう。
なお、土地選びからハウスメーカー選び、資金計画まで住まいづくりを総合的に整理したい方は、ウチつくの「オンライン相談サービス」の利用がおすすめです。
ウチつくでは専用の土地検索アプリで希望エリアの候補地や相場を一緒に確認できるほか、注文住宅に詳しい担当者に相談しながら自分に合った住宅メーカーはどこか、資金計画をどのように建てるかを決めていくことができます。土地選びの悩みをチャンスに変える第一歩として、まずは住まいづくりの無料相談から始めてみましょう。
注文住宅の土地選び・資金計画に
お悩みはありませんか?
「ウチつく」オンライン無料相談なら
プロが徹底サポート!
-
家づくりの準備がワンストップで整う
段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。
-
住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける
専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。
-
最短1時間・オンラインで気軽に相談できる
スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。
ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで
幅広いラインアップ
ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!
参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象


Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!


Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!
納得・安心の家づくりなら
「ウチつく」にお任せください!
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事