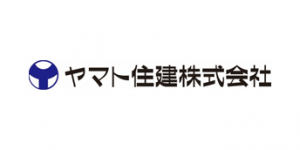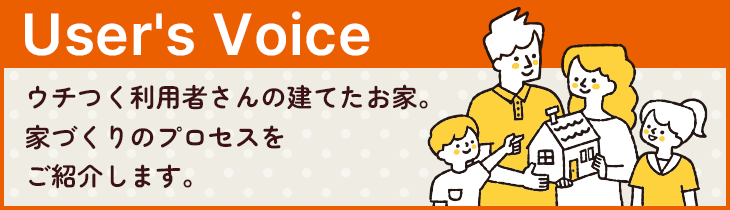防音室を新築住宅に取り入れるといくらかかる?費用相場と注意点を紹介
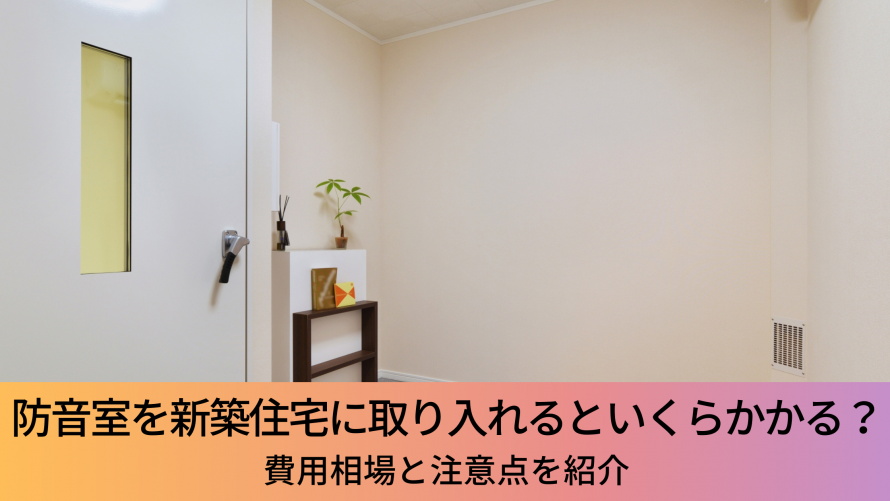
楽器演奏や映画鑑賞、テレワークでのリモート会議など、音量について周囲へ配慮が必要な仕事をお持ちだったり、趣味を存分に楽しみたい方にとって「新築購入時に防音室の設置をする」のかは生活の質を大きく向上させる選択です。この記事では、新築住宅における防音室の設置費用や注意点、メリット・デメリットを詳しく解説します。
防音室を設置するのにかかる具体的な費用や、注意すべきポイントをあらかじめ把握し快適な生活を実現するための計画をスムーズに進めていきましょう。
目次
防音室について

「防音室」と聞くと、高価で専門的なイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。確かに防音室は一般的な部屋とは違った構造を持ち、専門知識がないと適切な選択が難しい面があります。
ですが自分の目的に合った防音室はどんなものなのかを理解することで、必要以上のコストをかけず、効果的な防音空間を実現できます。
そのためここでは、防音室の基本的な知識と種類、構造について詳しく見ていきましょう。
防音室とは
防音室は、室外へ音が漏れるのを防ぐことを主な目的とした特別な構造を持つ部屋です。楽器演奏や映画鑑賞、ゲームなど、大きな音が出る趣味を持つ方に適した空間となります。
防音対策には、主に「空気伝搬音」と「固体伝搬音」の2種類の音を防ぐ構造が必要です。空気伝搬音は空気を通じて伝わる音、固体伝搬音は壁や床などの固体を通じて伝わる音を指します。理想的な防音室はこの両方に対応した構造を持っています。
ただし、換気設備などが必要な点から完全に防音できない部分があることを理解しておきましょう。防音室には「組立式(ユニット式簡易防音室)」と「フルオーダー式」の2種類があり、用途や予算に応じて選択が可能です。
遮音と吸音の違い
防音室の建築を考える際に理解しておく必要があるのが「遮音」と「吸音」の違いです。
遮音は音を遮断し、反射させることを言います。一般的に硬い材質を使用することで音が透過することを防ぎます。
一方、吸音は音を吸収し、音の振動を抑えることを意味します。こちらは柔らかい材質を使用することが多いです。
防音室では、この遮音と吸音のバランスが非常に重要です。遮音だけを重視すると室内で音が反響しすぎてしまい、逆に吸音しすぎると音が響かず、音色がわかりにくくなる場合があります。特に楽器演奏などで使用する部屋では、適切なバランスを保つことが音楽体験の質を左右します。
また、この2つに加えて振動を抑える「防振」も重要な要素となる場合があります。特にドラムなどの振動が大きい楽器を使用する場合は、防振対策も欠かせません。
遮音等級と防音性能について
防音性能を数値で表す指標として使われるのが「遮音等級」です。これは、隣り合う部屋同士の遮音性能を示す値で「D値」または「Dr値」で表されます。
遮音等級は、壁に入る音と壁を透過する音の音圧レベルをデシベル(dB)で表し、その差を求めることで算出されます。たとえば、D-50は「50デシベルぶん、音を遮断する」ことを意味し、数値が大きいほど遮音性能が高いです。
適切な遮音等級は目的によって大きく変わります。たとえば、通常の会話程度であればD-40程度でも十分ですが、ドラムなどの大音量の楽器演奏ではD-65以上が必要になることもあります。家の周辺環境や自分のライフスタイルによっても設定すべき遮音等級は変わってくるため、その部屋で何をしたいのかに合わせて専門家に相談してみましょう。
新築住宅に防音室を設置するメリット

新築住宅の計画段階で多くの方が悩むのが「防音室は本当に必要なのか」という点です。将来的な使用頻度も不透明な場合は初期投資の大きさなどが気になって設置に迷ってしまう方も多いでしょう。しかし、防音室には様々な用途に活用できるメリットがあります。長期的な視点で見ると価値のある投資となるなど、想像以上に生活の質の向上につながることもあるでしょう。
ここからはそんなメリットについて4つを詳しく説明します。
大音量で音楽・映画・ゲームを楽しめる
防音室の最大のメリットは、時間帯を気にせず大音量で映画や音楽を楽しめることです。一般的な住宅では、夜間や早朝に大きな音を出すことは難しいですが、防音室があれば気兼ねなく楽しむことができます。
映画鑑賞では臨場感あふれるサウンドを体験でき、オンラインゲームでのボイスチャットも周囲を気にせず楽しめます。家族や隣家への配慮をする必要がないため、エンターテイメントを最大限に楽しめる環境が整うでしょう。
近隣トラブルを防止できる
音に関する近隣トラブルは毎年増加しているといわれています。実際に、国土交通省の調査によると住宅の騒音トラブルは相談件数全体の約20%を占めているそうです。防音室を設置することで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。
音の感じ方は人によって大きく違うため、自分では「そこまで大きくない」と思っていても、他の人にとっては気になる騒音になることがあります。会議などで声や音が頻繁に出る仕事をリモートワークで行う方や、楽器演奏や音楽鑑賞、ゲームなどの趣味を持つ方にとって、時間を気にせず活動できる環境は大きな価値があるでしょう。
仕事や勉強に集中できる空間になる
防音室は音を「外に出さない」だけではなく、外部からの音を「遮断する」効果もあります。そのため、集中力を必要とする仕事や勉強に最適な環境になります。
たとえば、リモートワーク中のオンライン会議で家族の声が入る心配がなくなるというのは大きなメリットです。
また、プライベート空間との明確な区切りがあることで、メリハリのある生活が送りやすくなり、作業効率の向上にもつながります。
楽器を演奏・保管できる
楽器を演奏する方にとって、周りへの迷惑を気にすることなく理想的な環境で演奏できることはとてもうれしいことです。防音室では、楽器の種類に合わせた音響設計が可能なため、最適な演奏環境を整えることができます。
また、多くの楽器は温度や湿度に敏感です。防音室では環境管理がしやすいため、楽器を良好な状態で保管できる場所としても活用できます。演奏しないときの楽器の置き場としても便利で、大切な楽器を守りながら、いつでも演奏できる環境が整います。
新築住宅に防音室を設置するデメリット

ここまで防音室のメリットを伝えてきましたが、費用面や空間の制約、将来的な使い勝手など、設置するかどうかを判断をするためには避けて通れないデメリットもあります。多くの人が直面する問題点を事前に理解しておかなければ、後悔するリスクが高まってしまうでしょう。
これらのデメリットを正しく認識し、対策をすることで、多くの課題は解決または軽くすることが可能です。ここでは、防音室設置に伴う主なデメリットとその対処法について詳しく解説していきます。
設置費用がかかる
防音室の最大のデメリットは、一般的な部屋に比べて設置コストが高くなることです。特に高い遮音性能を求める場合、その費用は更に高額になります。
規模や仕様によって費用は大きく変わりますが、本当に必要な空間なのか、また高い遮音等級が本当に必要なのかを慎重に検討する必要があります。浮き構造などの特殊な工法は費用が高くなる傾向があるため、予算との兼ね合いも重要です。
施工会社によって工事内容や金額が違ってくるため、複数社の見積もりを取りましょう。この後に紹介する費用相場も参考にしながら、予算計画を立てていくことが重要です。
居住スペースが狭くなる
防音対策のためには壁や天井を厚くする必要があるため、同じ外側の寸法でも壁や天井の厚みの分だけ実際に使える空間は狭くなります。一般的に、防音壁は通常の壁より10〜15センチメートル厚くなります。また、防音効果を高めるために窓を小さくするか、あるいは設置しないことも多く、閉塞感を感じることもあるでしょう。
実際に確保できる空間の広さを事前に確認し、快適に過ごせる空間づくりを工夫することが重要です。内装や照明によって開放感を演出するなど、心理的な狭さを軽くする工夫も検討すると良いでしょう。
暑さ対策が必要
防音室は気密性が高いため、特に夏場は熱がこもりやすいというデメリットがあり通常の部屋より温度が高くなりやすいです。そのため、ほとんどの場合エアコンの設置が必須となります。
ただし、通常のエアコンの設置方法では防音性能を損なう可能性があるため、防音室に適した特殊な方法でエアコンを設置する必要があります。なお、長時間の使用が頻繁な場合は冷却のためだけでなく、新鮮な空気を取り入れるための換気システムもきちんと配慮したエアコンであるか、も検討のポイントの1つです。
使わなくなった後に困る
多額のコストをかけて作った防音室も、趣味の変化やライフスタイルの変化により、使わなくなる可能性があります。たとえば、子どもの楽器練習のために作ったものの、興味が移って使用頻度が減ってしまうケースなどです。
このリスクを軽減するためには、趣味部屋や書斎など、多目的に使える設計を検討すると良いでしょう。防音室で映画鑑賞、オンラインゲーム、テレワークなど複数の用途に活用できるよう計画することが重要です。また、組立式防音室であれば、将来的に撤去したり、移設することが可能なため、柔軟性が高いというメリットがあります。
新築住宅の防音室にかかる費用相場

防音室の設置を検討する際、最も気になるのは「いったいいくらかかるのか」という点でしょう。予算計画なしに進めると、想定外の高額出費に驚くことになりかねません。特に新築時は他の工事費用との兼ね合いもあり、適切な予算配分が求められます。
しかし、用途や求める性能によって費用は大きく変動するため、一概に「これくらい」と言い切れない難しさがあります。ここでは、防音室の種類や目的別に費用の相場を紹介します。
6畳程度の防音室の費用相場
新築住宅に防音室を設置する場合、坪あたり100万円からが一般的な目安となります。たとえば6畳(約3坪)の防音室を設ける場合、250万円以上かかるでしょう。
より手頃な選択肢として、組立式防音室であれば50万円程度から導入することができます。ただし、組立式は防音性能やデザイン性において一体型に比べると制限があることを理解しておく必要があります。
費用は用途や求める防音性能によって大きく変動するため、事前に施工会社に相談しておきましょう。
防音性能のグレード別の費用比較
防音性能のグレードによって、必要な費用は大きく変わってきます。楽器別の一般的な費用相場は、以下のとおりです。
- ピアノ、管楽器:約250万円~300万円
- ドラム:約350万円~420万円
これはあくまで目安であり、広さや内装、設備によって費用は大きく変動します。特にドラムなど振動の大きい楽器を演奏する場合は、床の浮き構造などが必要となるため、コストが高くなる傾向があります。
より高い防音性能を求めると費用は比例して高くなるでしょう。予算と必要な防音性能のバランスを考えて、適切な選択をすることが重要です。
新築時に防音室を設置する際の注意点

防音室の設置を決めたものの、具体的にどう進めれば良いのか迷う方は多いはずです。設計ミスや施工不良による音漏れ、換気不足による結露やカビの発生など、知識不足による失敗事例は後を絶ちません。こうした問題は、事前の適切な計画と専門家との綿密な打ち合わせによって回避できます。
経験豊富な住宅メーカーに施工を依頼し、使用目的に合った仕様を選ぶことが成功への近道です。ここでは、新築時に防音室を設置する際に押さえておくべき重要なポイントについて詳しく見ていきましょう。
防音室を何に使うか決める
防音室の設計において最も重要なのは、用途を明確にすることです。用途によって必要な防音対策が大きく変わるためです。
たとえば、楽器の種類によって音の響き方が違ってくるので、設計や使用する材料も変わってきます。弦楽器とドラムでは、必要な防音性能や室内の音響環境が全く違います。また、録音や収録をする場合は、外からの音も完全に遮断することが必要です。
細かい条件を整理し、施工会社と共有することで、理想的な防音室の実現が可能になります。事前の打ち合わせでは、できるだけ具体的に使用目的を伝えることがポイントです。
換気システムを確保する
防音室は基本的に密閉空間となるため、換気システムの確保は非常に重要です。適切な換気ができないと、空気が悪くなるだけではなく、カビや結露の原因にもなります。
換気扇や通気口をつくり、こまめに換気を行うことが必要です。ただし、一般的な換気口では音漏れの原因となる可能性があるため、防音性を損なわない専用の換気システムを選ぶ必要があるでしょう。
また、建物本体の換気経路とは別に、防音室独自の換気経路を作ることで、より効果的な換気が可能になります。長時間使用することを考えると、快適な空気環境を維持するための換気設計は必須です。
施工実績が豊富な会社を選ぶ
防音室の施工は専門性の高い工事です。そのため、住宅メーカーや一般的な工務店だけではなく、防音室専門の施工会社も検討しましょう。
実績や施工例が豊富な会社を選ぶことで、失敗のリスクを減らすことができます。特に防音に対して専門知識のある会社であれば、より効果的かつ効率的な提案が期待できます。
また、防音性能が確保されているかを工事完了後に確認するアフターサービスの有無も重要なチェックポイントです。実際に音を出して測定し、期待通りの性能が得られているかを確認できるサービスを提供している会社が理想的です。
まとめ|新築住宅に防音室を設置する際のポイントを押さえておこう

防音室の設置は、多くの専門知識と適切な判断が求められます。予算オーバーや期待した防音効果が得られないなど、失敗したときのリスクも少なくありません。しかし、適切な知識を身につけ、信頼できる専門家と連携することで、これらの問題は解決することができます。
防音室の設計・施工は、専門知識を持った住宅メーカー選びが成功のカギとなります。新築時から防音室を計画する場合、要望に柔軟に対応してくれる住宅メーカーを選ぶことが重要です。
こういったこだわりのある家づくりを検討している方には、実現できる住宅メーカー選びを家づくりの専門家が無料でアドバイスする、ウチつくの「オンライン相談サービス」が最適です。専門家と相談しながら、理想の防音室が作れる住宅メーカーを見つけて後悔のない家づくりを実現しましょう。
注文住宅の土地選び・資金計画に
お悩みはありませんか?
「ウチつく」オンライン無料相談なら
プロが徹底サポート!
-
家づくりの準備がワンストップで整う
段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。
-
住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける
専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。
-
最短1時間・オンラインで気軽に相談できる
スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。
ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで
幅広いラインアップ
ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!
参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象


Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!


Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!
納得・安心の家づくりなら
「ウチつく」にお任せください!
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事