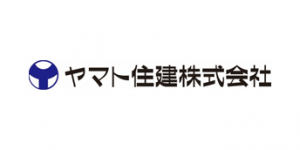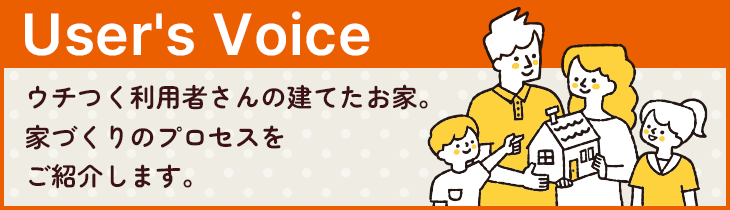家を建てた後にかかる税金は?活用できる節税対策も合わせて解説

家を建てると、住宅ローンの返済以外にもさまざまな税金がかかります。中でも固定資産税や都市計画税は毎年継続して支払う必要があります。負担を軽減できる制度を知らないまま家を建ててしまうと、予想以上の出費に頭を悩ませることにもなりかねません。
この記事では、家を建てた後にかかる税金の種類や金額の目安を紹介します。また、減税措置や給付金制度など、税負担を軽減できる制度についても解説するため、長期的な資金計画を立てる際に役立つ情報を得ることができるでしょう。
目次
家を建てた後に毎年かかる税金は2種類

家を建てた後の税金について、具体的な金額がイメージできず不安を感じている方は多いのではないでしょうか。住宅を所有すると毎年支払う必要がある税金は2種類あり、その内容をしっかりと理解しておくことで、将来の家計の見通しを立てやすくなります。
ここでは、固定資産税と都市計画税について、それぞれの計算方法や支払い時期を詳しく解説します。
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人に課される税金です。納付については、自治体から4月から6月頃に届く納税通知書に従って支払いを行います。納付方法は年1回の一括払いか、4回の分割払いかを選ぶことができるため、自身の状況に合わせて選択するとよいでしょう。
税額は評価額に1.4%の税率を掛けて計算されます。3年に1度評価額の見直しがあり、地価の変動があれば土地の評価額も変わるため、その年の固定資産税額も変動する可能性があります。
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業の費用を賄うために設けられた市町村税です。固定資産税と同様に毎年1月1日時点の不動産所有者に課税され、納付書も固定資産税と一緒に送られてきます。税額は資産の評価額に税率を掛けて算出され、税率は市町村によって異なりますが最高で0.3%に定められています。
ただし、市街化調整区域の土地や建物には課税されないため、該当地域の居住者は都市計画税を支払う必要はありません。前もって自身の土地が課税対象となるかを確認し、納税に備えることが大切です。
家の購入時や新築時にかかる税金

住宅を購入したり新築したりする際には、さまざまな税金がかかるため、事前に把握しておく必要があります。具体的には、契約時の印紙税から始まり、所有権の移転時には登録免許税、そして不動産取得税など、複数の税金の支払いがあります。
ここでは、それぞれの税金について、いつ、どのくらいの金額を支払う必要があるのかをわかりやすく解説します。
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約書や建築請負契約書、住宅ローンの契約書を作成する際に必要となる税金です。納税方法は契約書に収入印紙を貼付し消印することで完了します。例えば、3,000万円の注文住宅を建てる場合、建築請負契約書には2万円分の印紙が必要となりますが、軽減措置を利用すると1万円で済みます。
このように契約金額に応じて税額が定められているため、事前に必要な印紙の額面を確認しておくことが大切です。契約時には適切な金額の収入印紙を用意し、納税手続きを行いましょう。
登録免許税
登録免許税は、土地や建物の所有権を登記する際に必要となる税金です。納付方法は、金融機関での支払いか、3万円以下の場合は収入印紙の印紙納付ができます。新築住宅の場合、所有権保存登記には固定資産税評価額の0.4%、中古住宅の売買では所有権移転登記として建物や土地の評価額の2%がそれぞれ必要です。
また、住宅ローンを利用する場合は、抵当権設定登記の税額として借入額の0.4%が加算されます。登記手続きは通常、物件の引渡し日に行われるため、その時点で納税する必要があります。不動産会社や司法書士と相談しながら、必要な税額を事前に把握し、登記がスムーズに進められるよう準備をしておくことが大切です。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を新たに取得した際に一度だけ課される税金です。税額は取得した不動産の固定資産税評価額に税率4%を掛けて計算されますが、住宅の場合はさまざまな軽減措置が用意されています。
納税のタイミングについては、不動産の引き渡しから数か月後に都道府県から納付書が届きます。引き渡しから1年以上経過してから納付書が届くこともあるため、納税資金は別途確保しておきましょう。
家を建てた後に負担軽減のために活用したい制度

住宅購入後の税負担に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。住宅を所有すると複数の税金がかかりますが、適切な制度を活用することで、その負担を抑えることができます。
固定資産税や不動産取得税など、さまざまな税金に対して設けられている減税措置や、給付金・補助金制度について詳しく解説します。
減税措置を利用する
家を建てた後の税金負担を軽減するため、さまざまな減税措置が用意されています。代表的なものとしては、住宅ローン控除による所得税の減額や、不動産取得税の課税標準額からの控除がなどです。
また、登録免許税は通常の税率2%が1.5%に軽減され、固定資産税は新築から3年間、税額が2分の1になる制度を利用できます。これらの制度を活用するには、床面積が50平方メートル以上といった条件や、申告手続きが必要となります。
減税措置の中には期限付きのものもあるため、適用期限を確認し、必要書類を早めに準備しておくことが重要です。
補助金制度を活用する
住宅購入時の負担を軽減するには、自治体が提供するさまざまな補助金制度を活用することが有効です。例えば、高断熱や太陽光発電などの省エネ設備を導入する住宅には補助金が支給され、子育て世帯向けには住宅支援制度が用意されています。(※予算条件に達したため2025年7月22日に受付終了)
これらの制度は地域によって内容や支給金額が異なり、多くの場合は年度ごとの予算枠や申請期限が設定されています。また、工事着工前の申請が必要となるケースも多いため、建築計画の早い段階から地域の自治体窓口やハウスメーカーに相談し、利用可能な制度を把握しておくことが大切です。制度を上手に活用することで、住宅取得の費用負担を大きく抑えることができます。
固定資産税を抑えるためのポイント

毎年かかる固定資産税の負担を少しでも抑えたいと考えている方は多いのではないでしょうか。固定資産税は住宅の設計や建築時の対応、支払い方法の工夫など、いくつかのポイントを押さえることで軽減できる可能性があります。
ここでは、固定資産税を抑えるための具体的な方法を5つ紹介します。
シンプルな家づくりにする
シンプルな住宅設計は、機能性を損なわずに税負担を抑える効果的な方法です。家のかたちを凹凸のない四角にし、併せて床面積を必要最小限に抑えることで、建物の固定資産税評価額を下げることができ、長期的な支出を軽減することが可能です。
たとえば、自治体にもよりますが、天井高1.4メートル以下のロフトやスキップフロアは床面積にカウントされないため、収納や書斎スペースとして活用できます。
長期優良住宅にする
長期優良住宅の認定を受けることで、通常の新築住宅より手厚い税制優遇を受けることができます。一般的な新築住宅の固定資産税は3年間2分の1となりますが、長期優良住宅の場合はこの期間が5年間に延長され、大きな節税効果が期待できるでしょう。
ただし、長期優良住宅の認定には高い耐久性や省エネ性能などの厳しい基準を満たす必要があり、建築コストは一般的な住宅より増加します。そのため、建築時の追加コストと税制優遇による節税効果を比較検討し、長期的な視点で判断することが大切です。優れた性能により将来的な修繕費用も抑えられるため、ライフサイクルコスト全体でのメリットを考える必要があります。
家屋調査はきちんと対応
家屋調査における適切な対応は、正確な固定資産税評価額の算出につながります。固定資産税は定められた計算式で算出されますが、実際の評価は調査員によって行われるため、コミュニケーションが重要です。
調査の際には、建物の構造や設備について正確な情報を提供し、質問には丁寧に回答することで、適切な評価を受けることができます。また、算出された評価額については、計算方法や金額に誤りがないか、自身でも確認することが大切です。
クレジットカードで支払いをする
クレジットカードで固定資産税を支払うことは、賢い方法です。多くの年会費無料のクレジットカードは1%程度のポイント還元率を設定しており、年間20万円の固定資産税をカード払いにすることで、2,000円相当のポイントを獲得できます。
注文住宅は一般的に長期間居住することを前提とするため、30年間継続してカード払いを行えば、累計で6万円分のポイントが貯まることになります。これは直接的な節税ではありませんが、固定資産税の実質的な負担を軽減する効果があります。
支払い方法を工夫することで、長期的な家計の負担を少しでも抑えることができるため、積極的な活用を検討する価値があります。
1月1日時点の土地の状態に注意する
固定資産税の課税は、毎年1月1日時点の土地の状況に基づいて決定されるため、建物の建築タイミングが税額に大きな影響を与えます。1月1日の時点で建物が建っていなければ、更地として扱われます。
住宅用地としての軽減措置を受けるためには、この基準日までに建物が建っていることが必要です。ただし、建て替えの場合には一定の条件下で救済措置が設けられており、軽減措置を継続することが可能です。
この救済措置を利用するには申請手続きが必要となるため、建て替えを計画する際は、事前に各自治体の窓口で制度の詳細を確認しておきましょう。
まとめ|家を建てた後の税金も計算して資金計画を立てよう

この記事では、家を建てた後にかかる税金について解説しました。毎年支払う必要がある固定資産税と都市計画税、また家の購入時や新築時に発生する印紙税、登録免許税、不動産取得税について紹介しています。
これらの税金は住宅ローンの返済と同様に大きな負担となりますが、住宅ローン控除や減税措置、給付金制度などを活用することで、その負担を軽減することができます。特に固定資産税は、長期にわたって支払い続ける税金のため、シンプルな家づくりや長期優良住宅の検討など、さまざまな工夫をすることで税額を抑えることが可能です。
家づくりの際は、建築費用だけでなく、その後にかかる税金も含めた長期的な資金計画を立てることが大切です。
注文住宅の土地選び・資金計画に
お悩みはありませんか?
「ウチつく」オンライン無料相談なら
プロが徹底サポート!
-
家づくりの準備がワンストップで整う
段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。
-
住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける
専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。
-
最短1時間・オンラインで気軽に相談できる
スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。
ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで
幅広いラインアップ
ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!
参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象


Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!


Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!
納得・安心の家づくりなら
「ウチつく」にお任せください!
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事