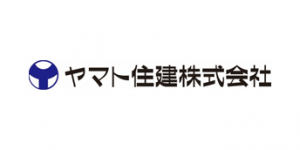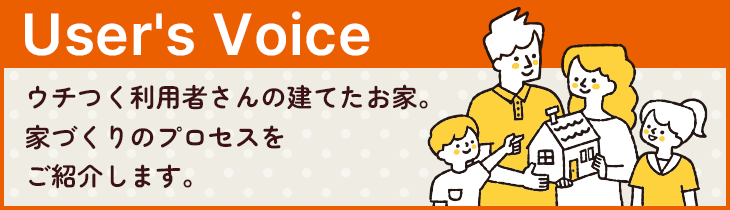床断熱と基礎断熱の違いは?メリット・デメリットやコストまで徹底比較

家を建てる際、床断熱と基礎断熱のどちらを選ぶべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。どちらも床下の断熱の工法ですが、施工方法や費用、効果が異なります。
この記事では、それぞれの工法の特徴を比較し、メリット・デメリットを詳しく解説します。快適な住環境づくりのために、最適な断熱工法を見つけましょう。
床断熱と基礎断熱の違い

床断熱と基礎断熱は、同じ断熱工法でも施工方法や特徴が大きく異なります。床断熱は床下に断熱材を敷き詰める工法で、基礎断熱は基礎の外周部に断熱材を設置する工法です。工法の違いにより、費用や施工期間、快適性にも大きな差が出てきます。
ここでは、それぞれの工法の特徴やコストを比較し、どちらを選ぶべきかを具体的に解説します。家づくりにおいて重要な断熱工法の選択ができるようになるでしょう。
床断熱と基礎断熱のコスト比較
床下断熱と基礎断熱のコストは、使用する材料によっての差はあるものの、大きな差はありません。一般的な断熱材であるポリスチレンフォームやウレタンフォームの場合、1平方メートルあたり3,000~6,000円程度で、100平方メートルの施工では約49~60万円の費用が必要です。より高性能なセルロースファイバーを選択すると、1平方メートルあたり6,000~9,000円となり、100平方メートルで約60~90万円になります。
床断熱と基礎断熱のどちらを選ぶべき?
床断熱と基礎断熱の選択は、住んでいる地域の気候や生活スタイルにより選ぶ事が重要です。床断熱は、シロアリ被害の防止や床暖房の設置がしやすく、特に暖かい地域に適しています。
一方、基礎断熱は年間を通じて室温を快適に保ちやすいため、全館空調システムとの相性が良く、空調コストの削減効果も期待できます。ただし、定期的な点検や維持管理が必要になります。
また、床下浸水のリスクが低い地域での導入がおすすめです。快適な住環境を実現するため、これらの特徴を踏まえて選択しましょう。
床断熱と基礎断熱のメリット・デメリット

床断熱と基礎断熱は、それぞれの工法ならではのメリットとデメリットがあり、住まいの快適さに大きく影響します。メリットを活かし、デメリットに上手く対応することで、より良い住環境を実現できるでしょう。
ここでは、床断熱と基礎断熱のメリット・デメリットを、施工のしやすさ、メンテナンス性、温度管理、コストなど、さまざまな観点から詳しく解説します。それぞれの特徴を理解することで、あなたの家に最適な断熱工法を選ぶことができるでしょう。
床断熱のメリット・デメリット
床断熱工法は、断熱性能と気密性の確保が重要となります。配管の貫通部や床下点検口などの気密処理には高度な技術が必要で、施工会社の経験が重要です。
床断熱のメリットは、工事費用を抑えられることと、断熱材の交換や補修が比較的容易な点です。また、床下空間を利用して配管類を自由に配置できるため、設備の設計の自由度が高くなります。
また、床下の梁と梁の間に設置する断熱材の厚さには制限があるため、高い断熱性能を求める場合は工夫が必要となるでしょう。床下は断熱区画の外側となるため、床下エアコンなどの設置ができず、床暖房を使用する場合は熱損失が大きくなります。
床断熱にすることで床下空間自体が外気温の影響を受けやすい環境となるため、配管の凍結防止や定期的なメンテナンスが必要になります。特に床下の水回りは温度が下がりやすく湿気も多いため、シロアリ被害のリスクが高まる可能性があります。また、床下が虫や小動物にとって居心地の良い環境となるため、防虫対策も重要です。
基礎断熱のメリット・デメリット
基礎断熱工法の特徴は、床下と室内の温度・湿度をほぼ同一に保てる点にあります。床下エアコンや床下放熱器の設置が可能で、足元が高めに保たれるため、快適な室内環境を実現できます。また、高い基礎を活かして床下を収納スペースとして活用でき、気密性能も確保しやすいのがメリットです。
一方で、最大のデメリットはシロアリです。断熱材はシロアリに弱く、蟻道となる恐れがあります。さらに、床下の高湿度によるカビの発生リスクがあります。
基礎断熱で失敗しないためのポイント

基礎断熱は効果的な断熱工法ですが、施工方法や材料の選び方を誤ると、シロアリの被害や湿気の問題が発生する可能性があります。また、断熱効果を最大限に引き出すためには、換気システムや断熱材の選び方など、いくつかの重要なポイントに注意が必要です。
ここでは、基礎断熱で失敗をしないポイントを、具体的な対策とともに解説します。ポイントを理解することで、長期間にわたって快適な住環境を維持できるようになるでしょう。
防蟻処理された断熱材を選ぶ
シロアリ対策として、防蟻処理された断熱材を選びましょう。日本では主に3種類の防蟻断熱材があり、シロアリの歯が届かない素材、ネオニコチノイド薬剤を含む素材、そしてホウ酸系の素材が使われています。
断熱材の設置時には、防蟻剤入りのシリコンやウレタンスプレーを基礎との接合部に使用することで、さらなる予防効果が期待できます。特にシロアリ被害の多い地域では、基礎周辺に薬剤注入用のパイプを設置し、定期的な防蟻処理を行うことも有効な対策です。施工前に使用する断熱材の種類や防蟻処理の方法について、建築会社に確認することが大切です。
換気システムにも注目する
換気システムは建築基準法により24時間換気が義務付けられていますが、基礎断熱と組み合わせることで、さらに効果的な空気環境を実現できます。また、高性能なフィルターを備えた換気システムなら、花粉やPM2.5などの有害物質も除去でき、より快適な住空間を作り出せます。
床下の湿気対策を徹底する
基礎断熱工法を採用した住宅では、床下の湿気対策が重要な課題となります。床下空間は密閉されやすく、湿気がこもることでカビの発生リスクが高まるため、24時間稼働の床下換気システムの導入や床面への換気口の設置が効果的です。
また、除湿機能付きエアコンを活用することで、細かい湿度管理が可能になります。暖房器具の選択にも注意が必要で、特に石油ストーブは燃焼時に水蒸気を発生させるため、室内の湿度上昇につながります。適切な換気と除湿対策を組み合わせることで、快適な床下環境を維持できるでしょう。
断熱材の保証期間と内容を確認する
施工会社によって、断熱材の性能低下やシロアリ被害に対する保証期間や保証内容が異なるため、契約前の確認が重要となります。
具体的な保証期間や補償範囲、メンテナンス時の費用負担などについて、建築会社と詳しく話し合うことが必要です。また、保証の内容をしっかりと確認し、保証の条件や除外事項なども把握しておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。
基礎断熱にすると期待できる効果

基礎断熱を採用すると、年間を通じて住まいの快適性が大きく向上します。特に冬場は、床下からの冷気を防ぐことができ、床面の温度差が少なくなるため、快適に過ごせるでしょう。
ここでは、基礎断熱を選んだ場合に期待できる効果を解説します。温度管理の改善やヒートショック対策など、家族の健康と快適性を高める効果について詳しく見ていきましょう。
適切な温度管理ができる
基礎断熱工法は、年間を通じて快適な室内環境を実現できる優れた断熱方式です。冬場は床下空間も室内と同じように暖かく保たれるため、足元からの冷えを感じにくく、家族がリビングでゆっくりと過ごせる環境を作り出します。
また、夏季はエアコンの使用頻度を抑えられるメリットもあり、床下からの熱気の侵入を防ぐことで、自然な涼しさを保つことができるでしょう。このように、基礎断熱は季節を問わず快適な住空間になり、省エネ効果も期待できます。
ヒートショックの心配が減る
基礎断熱と全館空調の組み合わせは、家全体の温度を均一に保つことができるため、高齢者に深刻な健康リスクとなるヒートショックの予防に効果的です。特に寒い脱衣所やトイレなど、従来は温度差が生じやすかった場所でも快適な室温を維持できます。
さらに、高い気密性により室内の温かい空気が逃げにくいため、洗濯物の室内干しも効率的に行えます。雨天時でもエアコンを使用することで乾燥させることができ、生活の質が大きく向上します。
まとめ|床断熱と基礎断熱の違いを理解した上で自分に合った選択をしよう

この記事では、床断熱と基礎断熱の違いをはじめ、それぞれのメリット・デメリットやコストについて詳しく解説しました。床断熱は導入のしやすさとメンテナンスの容易さが魅力です。一方、基礎断熱は温度管理の効率性とヒートショック対策に優れています。
基礎断熱を選ぶ場合は、防蟻処理された断熱材の使用や換気システムの活用、床下の湿気対策など、いくつかの重要なポイントに注意が必要です。また、断熱材の保証期間や内容もしっかりと確認しましょう。
どちらの工法も一長一短があるため、自身の住環境や予算、メンテナンス性を考慮し、快適な住まいづくりのために最適な断熱工法を選びましょう。
注文住宅の土地選び・資金計画に
お悩みはありませんか?
「ウチつく」オンライン無料相談なら
プロが徹底サポート!
-
家づくりの準備がワンストップで整う
段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。
-
住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける
専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。
-
最短1時間・オンラインで気軽に相談できる
スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。
ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで
幅広いラインアップ
ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!
参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象


Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!


Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!
納得・安心の家づくりなら
「ウチつく」にお任せください!
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事