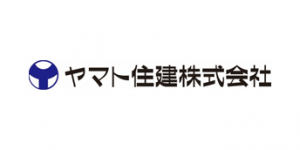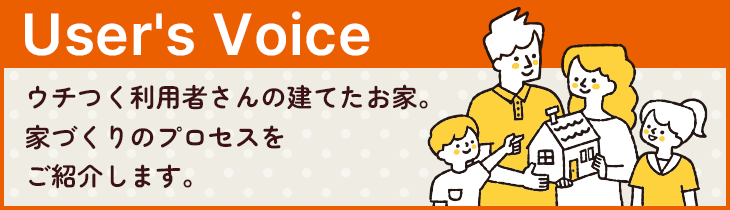土地購入時にかからない税金とは?非課税条件と節税ポイントを徹底解説

土地を購入する際にはさまざまな費用が必要ですが「土地自体には消費税がかからない」という話を聞いたことがあるでしょうか。土地を購入する時には他にもさまざまな税金や費用が発生します。どの項目に税金がかかり、どの項目が非課税なのか、正確に把握することが重要です。
この記事では、土地を購入する時にかからない税金や非課税となる条件について徹底解説します。この記事を読んで、土地選びから建築、長期の資金設計まで一貫して「ムダのない」資金計画を立てましょう。
目次
土地購入に関する税金について

土地の購入を検討する際、「どのような税金がかかるのか」「なぜ土地には消費税がかからないのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。これらの税金の仕組みを正しく理解することで、予算計画を立てやすくなり、思わぬ出費を防ぐことができます。
ここでは、土地の購入に関する基本的な税金の種類や、土地が消費税の非課税対象となる理由について詳しく見ていきましょう。
土地自体には消費税がかからない理由
土地の売買自体には消費税がかかりません。これには明確な理由があります。
消費税は、国内における事業者が事業として対価を得て行う取引で、消費に負担を求める税金です。土地は消費されるものではなく、供給量も固定されています。また、土地の価値は基本的に減少しないという風に扱われています。
このため、土地の取引そのものは消費税の課税対象外になります。ただし、土地の取引に関連するさまざまなサービスには消費税がかかる点に注意が必要です。
土地購入時に発生する主な税金の種類
土地を購入する際には、以下のような税金が発生します。
- 印紙税:不動産売買契約書や住宅ローン契約書を作成するときに課税される国税です。契約金額によって税額が変わります。
- 不動産取得税:土地や建物を取得したときに都道府県から課される地方税です。取得した不動産の価格をもとに計算されます。土地と建物、それぞれに課されるので注意が必要です。
- 固定資産税:毎年1月1日時点で土地などの不動産を所有している方に市町村から課される地方税です。
- 登録免許税:所有権移転登記などの不動産の登記のときに支払う国税です。固定資産税の評価額をもとに計算されます。
- 都市計画税:市街化区域内に土地や建物を持っている場合に課せられる地方税です。固定資産税と一緒に納付します。
また、土地の取引に関わるサービスにかかる消費税もあります。
- 仲介手数料にかかる消費税:不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかります。
- 住宅ローンの手数料にかかる消費税:住宅ローンの事務手数料にも消費税がかかります。
- 司法書士への手数料にかかる消費税:土地の売買で必要な登記を司法書士に依頼を行うための手数料にも消費税がかかります。
このようにいろいろな税金があるので、どの項目にどの税金がかかるのか、事前に把握しておきましょう。
非課税・免税・軽減措置の違い
税金に関する用語として「非課税」「免税」「軽減措置」という言葉があります。これらをきちんと違いを理解し、どのような場合に税金が免除されるのか、軽減されるのかを正確に把握することでよりよい対策をとることができるでしょう。
まず非課税とは、そもそも課税対象とならないことです。土地の売買そのものが消費税の非課税取引にあたります。
次に免税とは、本来であれば課税対象ですが、一定の条件を満たす場合に課税を免除されることです。たとえば、不動産取得税では、取得する不動産の価格が一定額以下の場合に免税となります。
最後に軽減措置とは、税率を下げる、または課税標準を低くすることで税負担を軽くする制度です。住宅用地に対する固定資産税の特例などがこれに該当します。
土地購入で消費税がかからない項目と課税される項目

土地を購入するときの費用に関して「すべてに消費税がかかる」と誤解している方も多く、余計な資金まで準備してしまうケースがあります。実際には土地そのものの価格には消費税はかかりませんが、関連するサービスやその手数料には税金がかかります。
この違いを把握することで、資金計画を正確に立てることができます。ここでは、土地購入における消費税の課税対象と非課税対象をきちんと区別し、実際にどの費用に消費税がかかるのかを詳しく見ていきましょう。
消費税が非課税となる項目
これらの項目には消費税はかかりません。
- 土地そのものの売買代金:先ほども話したとおり、土地の売買自体は消費税の非課税取引です。
- 印紙税:国税である印紙税自体にも消費税はかかりません。
- 登録免許税:登記に関する国税である登録免許税にも消費税はかかりません。
- 不動産取得税:地方税である不動産取得税にも消費税はかかりません。
- 固定資産税・都市計画税:これらの地方税にも消費税はかかりません。
- 住宅ローンの返済利息、保証料:金融商品に関する取引は消費税の非課税取引です。個人の賃貸の家賃、敷金、保証料:個人が貸主となる住宅の賃貸料なども消費税の非課税取引です。
- 火災保険料:保険料も消費税の非課税取引となります。
国税や地方税といった税金、利息や保証料、そして保険料は、消費税の課税対象外です。
消費税が課税される項目
一方、これらの項目には消費税がかかります。
- 不動産仲介手数料:不動産会社に支払う仲介手数料には消費税がかかります。
- 司法書士への報酬:登記手続きを司法書士に依頼する場合、その報酬には消費税がかかります。
- 土地家屋調査士への報酬:測量や調査を土地家屋調査士に依頼する場合、その報酬にも消費税がかかります。
- 住宅ローンの事務手数料:金融機関に支払うローンの事務手数料には消費税がかかります。
- 土地に埋まっている地下型の車庫:事業者が譲渡する場合、建物とみなされるため消費税がかかることがあります。
これらは、サービスの提供に対する対価として支払うものなので、消費税の課税対象となります。
建物付き土地購入の場合の消費税
土地と建物がセットになった物件を購入する場合は、消費税の取り扱いが少し複雑になります。
- 個人の売主から購入する場合:個人が売主の場合、つまりは中古物件を購入する場合は建物部分も含めて非課税となります。個人は消費税の課税事業者ではないためです。
- 課税事業者が売主の場合:不動産会社などの課税事業者から購入する場合、建物部分には消費税がかかります。土地部分は非課税です。
注意点として、建物と土地がセットになった建売住宅の場合、総額表示の中に建物の消費税が含まれていることがあります。建物付きの土地を購入する際は、どの部分に消費税がかかるのか、事前に確認することが大事になります。
土地購入で不動産取得税がかからないケース

不動産取得税は土地や建物を取得した際に課される税金ですが、いくつかの条件を満たすと、非課税になるケースがあります。ここではその非課税になるケースを紹介します。
価格が免税点未満の場合
取得する不動産の価格が免税点と呼ばれる一定額未満の場合、不動産取得税は課されません。
- 土地の場合:課税標準となるべき額が10万円未満
- 新築・増築・改築した建物の場合:課税標準となるべき額が23万円未満
- その他の建物の場合:課税標準となるべき額が12万円未満
ただし、1年以内に隣接する土地や建物を取得した場合は、それらを合算して判断されるので注意が必要です。
相続によって不動産を取得した場合
相続や遺産分割によって不動産を取得した場合も、不動産取得税は非課税となります。これは、相続による不動産の取得は「無償の所有権移転」であり、新たな経済的価値の移転とはみなされないためです。
包括遺贈の場合も、法定相続人以外が資産を引き継いでも非課税となります。包括遺贈とは、遺言によって相続財産の全部または一定割合を一括して受け継がせる遺贈で、受遺者は相続人と同じ権利義務を承継する方式のことです。ただし、遺言書で法定相続人以外に財産を譲る特定遺贈の場合は、課税対象となる点に注意が必要です。
土地区画整理の換地取得の場合
土地区画整理事業が終わり、土地を取得した場合も、不動産取得税は非課税となります。土地区画整理事業とは道路や公園などの公共施設を整備して、利用を促進するために国が行う事業のことです。これは、この事業終了後に取得した土地は、土地区画整理前の土地に代わるものであり、新たに土地を取得したとはみなされないためです。
特定の法人による事業用不動産取得の場合
特定の法人が、本来の事業のために不動産を取得した場合も、不動産取得税が非課税となるケースがあります。
- 学校法人が教育の場として不動産を取得した場合
- 宗教法人が境内地として不動産を取得した場合
- 社会福祉法人が老人ホーム等の社会福祉事業のために不動産を取得した場合
ただし、これらはあくまで本来の事業用に使用する場合のみ非課税となります。他の目的で使用する場合は課税対象となることがあります。
法人の合併または分割による不動産取得の場合
組織再編により法人が合併または分割し、不動産を取得した場合も、不動産取得税は非課税となります。これは、実質的には所有権が変わるだけで、新規取得ではないとみなされるためです。
土地購入後の税金控除で活用できる特例制度

土地購入後には、税金の負担を軽減するためのさまざまな特例制度があります。これらを上手に活用することで、税金の節約ができるでしょう。
住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、一定期間、所得税が控除される制度です。
- 控除期間は最大13年間(条件により変動)
- 年末のローン残高の0.7%(条件により変動)が所得税から控除される
- 控除を受けるには、初年度は確定申告が必要(2年目以降は年末調整で可能な場合もある)
- 原則50平方メートル以上ですが、2022年から合計所得金額1,000万円以下なら40平方メートル以上でも適用可能になりました
住宅ローン控除を受けるためには、住宅の取得後に確定申告を行う必要があります。必要書類や申告の時期について事前に確認しておくと良いでしょう。
居住用財産の買換え特例
居住用財産を売却して、新たに居住用財産を購入した場合に、譲渡益に対する課税を繰り延べる特例制度があります。
- 売却した住宅に10年以上住んでいた場合など、一定の要件を満たす必要がある
- 買い換え資産の取得価額が売却資産の譲渡価額以上である場合に適用される
- マイホームなどの居住用財産を売却したとき、その譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける3,000万円特別控除との併用はできません
この特例を利用することで、古い住宅の売却費用に対する課税を新しい住宅を購入するまで繰り延べることができます。ただし、特例の適用には細かい条件があるため、事前に専門家に相談することが重要です。
住宅用地の特例による固定資産税軽減措置
住宅が建っている土地である住宅用地に対しては、固定資産税の課税標準を軽減する特例があります。
- 200平方メートル以下の小規模住宅用地:課税標準が6分の1に軽減
- 200平方メートル以上の一般住宅用地:課税標準が3分の1に軽減
この特例は、住宅用地に対する税負担を軽減するための措置です。住宅を建てることで、土地にかかる固定資産税を大幅に抑えることができます。
耐震・バリアフリー・省エネ改修に関する特例制度
住宅の耐震化やバリアフリー化、省エネ改修を行った場合、固定資産税が減額される特例制度があります。
- 耐震改修:改修工事が完了した年の翌年度から一定の期間、固定資産税が減額
- バリアフリー改修:高齢者などのために行うバリアフリー改修工事を行った場合、一定の期間、固定資産税が減額
- 省エネ改修:省エネ改修工事を行った場合、一定の期間、固定資産税が減額
これらの特例を受けるためには、工事が完了した後、3ヶ月以内に市区町村への申告が必要です。対象となる工事や減額の割合は、自治体によって違う場合があるため、事前に確認することが重要です。
まとめ|土地購入時の税金を正しく理解して賢く節税しよう

土地を購入する時の税金について正しく理解することは、無駄な支出を抑え、効率的な資金計画を立てるために重要です。土地そのものに消費税はかかりませんが、仲介手数料、ローン事務手数料、登記費用などのサービスには消費税がかかります。
土地購入に関わる税金は複雑で、条件によって非課税となるケースや軽減措置が違ってきます。最新の制度や自分の状況に合った節税方法を知りたい方には、ウチつくの「オンライン相談サービス」がおすすめです。
お金の専門家でもある1級ファイナンシャルプランナーが無料でアドバイスし、土地購入から建築までの全体計画において最適な節税プランを提案します。専門家と一緒に、あなたにとって最適な注文住宅を建てる方法を見つけましょう。
注文住宅の土地選び・資金計画に
お悩みはありませんか?
「ウチつく」オンライン無料相談なら
プロが徹底サポート!
-
家づくりの準備がワンストップで整う
段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。
-
住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける
専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。
-
最短1時間・オンラインで気軽に相談できる
スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。
ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで
幅広いラインアップ
ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!
参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象


Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!


Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!
納得・安心の家づくりなら
「ウチつく」にお任せください!
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事