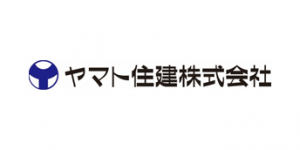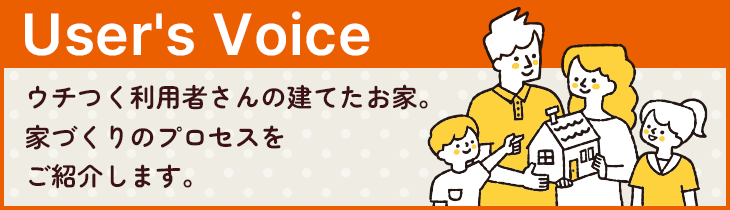セットバックとは?不動産購入前に確認すべきことをわかりやすく解説!

不動産広告や土地情報で「セットバック」という言葉をよく見ますよね。これは、建築基準法に従い、家を建てる際に土地の一部を道路として提供する制度であり、家づくりや不動産購入の計画に大きく影響する可能性があります。幅が狭い道路に面した土地の場合はセットバックが必要になりやすく、その分土地価格が比較的安く設定される反面、建築の制限や費用負担など気をつけたいポイントがあるのも事実です。
この記事では、セットバックの基本的な仕組みや必要になる理由、費用の内訳、注意点から具体的な活用方法まで解説します。計算方法も織り交ぜながら、セットバックの全体像がつかめるようサポートするので、これから不動産を購入しようと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
セットバックについて

セットバックは、建築基準法によって「土地の一部を道路として提供し、前面道路の幅を拡張する行為」として定義されています。この制度の背景には、火災や地震などの災害時に緊急車両が入ったり、安全な通行路や避難経路を確保する目的があります。
ここでは、セットバックの基本や、それと深く関わる「接道義務」について理解を深めていきましょう。
セットバックとは
セットバックとは、家を建築する際に、幅4メートル未満の狭い道路に面している土地の一部を後退させて道路として「提供」することを指します。単に敷地を後ろにずらすだけではなく、防災や街づくりの観点から、道路幅を広げるための重要な制度という位置づけです。具体的には、建築確認を取得する段階で「道路幅を4メートルにするためには何メートル後退すればよいか」を計算し、そのぶん敷地を削って道として扱います。
特に、消防車や救急車など緊急車両が問題なく通行できるための幅を確保するための措置でもあるため、災害時には大きな役割を果たします。セットバックが必要になる土地は、建築基準法の施行前から存在している道幅4メートル未満のいわゆる「2項道路」に面している場合が多く、その点が他の土地と大きく異なるポイントです。
建築基準法における接道義務とは
建築基準法第43条では「建物を建てる敷地は幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない」と規定されています。これを「接道義務」といい、建物を安全に使用できるようにするための大前提です。
しかし、古くからある狭い道の多くは、建築基準法の基準を満たしていません。そこで、それらの道を法律上の道路としてみなしつつ、将来的に4メートル幅へ拡張できるようにする仕組みが「2項道路」や「みなし道路」と呼ばれるものです。つまり、建築基準法施行前からある幅4メートル未満の道路に面している土地の場合は、セットバックによって幅を広げる必要があります。
2項道路とは
「2項道路」とは、建築基準法が施行される以前から存在していた幅4メートル未満の道路を指します。法律上は「建築基準法第42条第2項」で規定されるため、こうした名称がつけられています。これらの道路は、行政が指定することで一時的に法的な道路と見なされる扱いになりますが、あくまでも将来的には4メートルの道路へと拡張させることが前提です。
したがって、2項道路に面する敷地で新築や建て替えを行う際には、原則としてその敷地の一部をセットバックすることが義務づけられます。こうした仕組みによって、少しずつ街全体の道路幅を広げ、災害や緊急時の安全性を高めていこうというのが法律の狙いです。
セットバックが必要なケースと幅の計算方法
セットバックが求められるのは「幅4メートル未満の道路に接している土地」の場合ですが、どの程度セットバックするかは道路の向かい側の状況などによっても変わります。
対面が宅地の場合のセットバック幅の計算方法
もし道路の向かい側が宅地の場合は、通常「道路の中心線から2メートルの位置まで後退して4メートル幅を確保する」形でセットバックを行います。たとえば、現在の道幅が3メートルであれば、道路の中心から1.5メートルのところが基準線となり、向かい合う両者が0.5メートルずつ後退することで、最終的に4メートルにするのが一般的な考え方です。
このように、片側だけではなく両者が少しずつ協力して道路幅を確保するため、実際にどれくらいセットバックが必要になるかは道路の現状と対面の状況で異なります。また、厳密には自治体のルールや現地の測量結果によって変動することが多いため、正確な幅を知るには専門家による調査が不可欠です。
対面が崖・川などの場合のセットバック幅の計算方法
もし道路の反対側が崖や川、線路などで、そちら側にセットバックできない場合は、一方の所有者だけが道路幅4メートルを担うよう求められます。例えば、道幅が3メートルの場合、反対側が崖であれば崖側は動かせないため、あなたの土地だけで1メートル後退させなくてはなりません。
このケースでは、片側のみが大きくセットバックを負担することになるため、狭い道路に面している土地を購入する際は、対面状況を必ずチェックすることが重要です。崖や河川沿いの場合、想定以上にセットバックが広がり、実際の敷地が大幅に狭くなる可能性もあるので要注意となります。
セットバック済みの土地でも確認が必要な理由
不動産広告などに「セットバック済み」と書かれていても、注意が必要な場合があります。まず、そのセットバック部分がきちんと登記されているかどうかチェックしてください。図面や境界標と現地の状態が合っていなければ、後から思わぬトラブルに発展する恐れがあります。境界標とは境界の点や線の位置を表すための標識のことです。
さらに、実際にはまだ道路としての舗装が終わっていない場合や、近隣との話し合いが十分に行われていないケースもあります。特に境界の食い違いは、建て替え時や売却時に大きな障害になるので、役所や測量士、不動産会社など専門家のサポートを受け、現況と書類上の情報を丁寧に確認しておくことが大切です。
セットバックによるメリットとデメリット

セットバックには、土地所有者にとって土地の一部が使えなくなるというデメリットだけでなく、防災や街の景観への貢献など、地域全体の視点で見れば大きなメリットも存在します。双方を理解したうえで、どのように活用するかを検討することが重要です。
セットバックのメリット
1つ目のメリットは、道路幅が広がることで緊急車両が通行しやすくなり、災害時に素早く対応しやすくなる点です。また、歩行者の安全性も高まり、子どもが通学する道であれば親としても安心できるでしょう。
2つ目に、セットバック部分は固定資産税の減免対象となる場合があるため、税負担が軽減される可能性があります。これは自治体によって扱いが異なるため、事前に問い合わせておくと良いでしょう。
3つ目として、将来的に街全体の景観や利便性が向上し、資産価値が上がることも考えられます。最初は制限と感じやすい制度ですが、長い目で見れば地域コミュニティにとって重要な役割を果たしています。
セットバックのデメリット
デメリットの代表例は、セットバックした部分を含めた土地面積の減少にともなう建築制限です。後退する部分には家や塀を建てられないので、狭い敷地の場合はプランづくりが難しくなることがあります。
さらに、セットバック部分は道路扱いとなるため私的利用が禁止され、車を停めたりフェンスを設置したりできません。こうした制限によって、本来得られるはずの敷地活用の自由度が下がるのは否めないでしょう。
また、測量や舗装工事などの費用は自己負担が基本となる点も見逃せません。予算を考える際は、土地代だけでなくセットバック関連のコストも組み込む必要があるため、購入前にしっかりどれくらいお金がかかるか計算しておくことが大切です。
セットバック部分の固定資産税はどうなる?
セットバックした土地は「将来的に道路として利用される部分」とみなされるため、理論上は固定資産税の課税対象外になる場合があります。ただし、自動的に非課税となるわけではなく、多くの場合は自治体への申請が必要です。申請をしないままだと、セットバック部分に対しても課税され続ける可能性があるので、購入後は必ず役所の担当部署に確認しましょう。
また、使用状況によっては非課税にならないこともあるため「実際にどこまで道路として活用されるのか」「どのタイミングで申請手続きを行えばいいのか」を事前に把握しておくことが肝心です。
セットバックにかかる費用は誰が負担するのか?

セットバックを行うときには、土地の測量や分筆登記、道路として使うための舗装工事など、さまざまな費用が発生します。これらのコストは通常、土地所有者が負担するルールですが、自治体によっては部分的な助成制度が用意されていることもあります。
ここでは、具体的な費用の内訳と相場、そして補助を受けられる可能性について詳しく見ていきましょう。
セットバックにかかる費用の内訳
セットバックにかかる費用は、大きく分けて以下の4つです。
- 測量費用:専門家である測量士に依頼して、正確な境界を確定するための費用です。土地の形状や境界の状況によって、作業の難易度が変わるため費用にも幅があります。
- 分筆登記費用:後退させる部分を法的に切り離して、道路として扱うための登記手続きを行う費用です。登記を分けるという意味で、分筆登記と言います。不動産登記の専門家である司法書士などに依頼します。分筆登記をしていない場合は固定資産税の免税申請ができない可能性があるためきちんと行いましょう。
- 道路舗装費用:セットバックした部分をアスファルトやコンクリートで舗装して、実際に道路として利用できるようにするための費用です。地盤の状況によっては工事規模が大きくなる場合もあります。
- 既存構造物の撤去費用:セットバックエリアにフェンスや門、ブロック塀などがある場合、それらを取り壊すための費用がかかります。場合によっては樹木や庭石などの撤去が必要となることもあります。
セットバック費用の相場
一般的に、測量費用は10万円~30万円程度、分筆登記は5万~10万円程度、舗装工事は1平方メートルあたり数千円から1万円程度など、土地の大きさや形状によって差が出ます。また、撤去工事に関しては構造物の種類や量によっても大きく変動し、トータルで数十万~数百万円かかるケースも珍しくありません。
最終的な金額は地域や依頼先によって大きく異なるため、複数社から見積もりを取って比較するのがおすすめです。古い建物がある土地では想定外の撤去費用が発生する可能性もあるので、事前の調査と見積もりは念入りに行いましょう。
セットバック費用は自治体に一部負担してもらえる可能性がある
原則的には、セットバック費用は土地所有者が負担しますが、自治体によっては補助金や助成制度を設けているところがあります。これは、狭い道路を解消して防災力を高める取り組みを後押しする目的の一環です。
助成制度の内容は自治体ごとに異なり「舗装費用の一部を負担してくれる」「ブロック塀の撤去費用を補助する」といった形で実施されることが多いです。制度を利用するには条件がある場合があるので、購入前に自治体のホームページや窓口で情報を確認するか、不動産会社や建築会社に問い合わせると良いでしょう。
セットバックが必要な物件を購入する際の注意点

セットバックが必要な土地を購入する場合は、将来の建て替えや売却に関わるリスクや費用などを事前に理解し、納得のうえで契約することが大切です。ここでは、具体的にどんな点をチェックすべきかを整理してみましょう。
契約前に必ず確認すべきこと
セットバックが必要な物件を購入する際には、まず、セットバックの必要性とセットバック後の有効面積を必ず確認しましょう。また、建築基準法上の制限や、建ぺい率・容積率の制限も建てられる家の大きさにかかわってくるので重要な確認事項です。
さらに、セットバックにかかる費用や、自治体の補助制度の有無、セットバック後の固定資産税の扱いについても確認しておきましょう。これらの情報を事前に確認しておくことで、購入後のトラブルを避けることができます。
売却価格が低くなる可能性が高い
セットバックが必要な物件は、次に売却するときも同じ制限がかかるため、一般的に需要が限られ、売りにくいといわれています。売却できたとしても、価格は相場より低めになりがちです。
これは、不動産投資を目的に購入する場合にとっても大きなリスク要因となるため、出口戦略をしっかり考えておく必要があります。将来的に建て替えが必須になるとき、追加で費用や手間がかかる点にも留意が必要です。
セットバック部分の私的利用の禁止
セットバックして道路扱いになった部分については、駐車スペースや物置、塀などを置くことはもちろん、植木鉢ひとつであっても置くのは望ましくありません。そこは公共性を帯びたスペースであり、通行を妨げるようなものは設置できないルールとなっています。
そのため「自宅前の庭として使おう」と考えている場合は計画が崩れてしまうかもしれません。購入前にどのエリアがセットバック対象かを把握し、どのように利用できるかをしっかり確認することが重要です。
セットバックが必要な物件の購入を検討したほうが良いケース

セットバックがあると聞くと、デメリットばかりが目につきがちですが、条件によってはメリットがありながら、安全かつ安く土地を手に入れられる場合もあります。ここでは、どのような状況の人にセットバック物件が向いているのかを解説します。
予算を抑えたい
セットバックが必要な物件は、一般的に価格が安く設定される傾向にあります。そのため、予算を抑えたい場合や、相場よりも安く土地や物件を購入したい場合に検討すると良いでしょう。ただし、価格だけでなく、セットバックに必要な工事費用なども考慮に入れた上で、本当に割安かどうかを判断することが大切です。
セットバック後の敷地面積でも十分な広さがある
元々土地が広く、セットバック後でも十分な敷地面積を確保できる場合は、セットバックによる影響は少ないといえます。セットバック後の敷地面積で、希望の広さや間取りの家が建てられるか、事前に確認しておきましょう。また、セットバック後の土地でも、生活に支障がないか、じっくり検討することが大切です。
建て替えや売却の予定がない
既存の建物をそのまま利用する場合は、セットバックをする必要はありません。そのため、建て替えや売却の予定がないのであれば、セットバックのデメリットを気にせず住むことができます。ただし、防災上の理由から、セットバックを推奨する場合があることは覚えておきましょう。
特例や優遇措置を適用できる
一部の自治体では、セットバック部分の土地を買い取ったり、寄付として受け付けたりする場合があります。また、セットバックにかかる費用に対して、助成金や奨励金が支給されるケースもあります。これらの制度を利用することで、セットバックにかかる費用負担を軽減できる可能性があります。
まとめ|セットバックの特徴を理解して購入を検討しよう

セットバックは、土地の一部を道路として提供する行為であり、建築基準法に基づいて行われます。この記事では、セットバックの基本から、費用、注意点、そしてセットバックが必要な土地の活用法までを詳しく解説しました。
セットバックを理解することは、不動産取引において重要な知識となります。メリットとデメリットを理解し、自身の状況に合わせて、最適な判断をしましょう。
なお、土地選びにお悩みの方はウチつくの「オンライン相談サービス」の利用がオススメです。土地の探し方の解説はもちろん、専門家の視点からあなたにあった土地なのかの見極めるお手伝いも可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。
注文住宅の土地選び・資金計画に
お悩みはありませんか?
「ウチつく」オンライン無料相談なら
プロが徹底サポート!
-
家づくりの準備がワンストップで整う
段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。
-
住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける
専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。
-
最短1時間・オンラインで気軽に相談できる
スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。
ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで
幅広いラインアップ
ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!
参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象


Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!


Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!
納得・安心の家づくりなら
「ウチつく」にお任せください!
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事