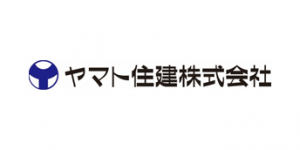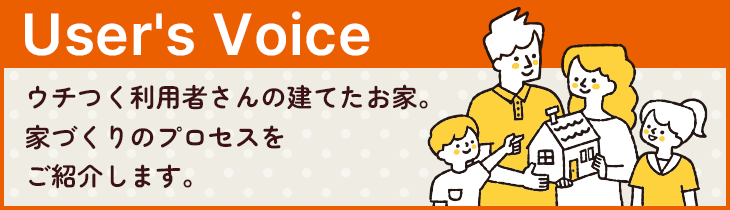農地転用できない土地とは?認可基準や活用法までわかりやすく解説

相続で農地を引き継いだものの、宅地として有効活用できず困っている方は多いのではないでしょうか。農地は原則として農業以外の目的で利用することができないため、転用が認められない土地も少なくありません。
また、近年は相続により農地を取得したものの、農業経験がなく、土地の活用方法に悩む方が増えています。
この記事では、農地転用できない土地の種類から、認可基準、転用できない場合の活用方法まで詳しく解説します。正しい知識を身につけることで、相続した農地を有効活用する方法が見つかるでしょう。
目次
農地転用について

相続や購入で農地を所有することになっても、すぐに宅地や駐車場として利用することはできません。これは、農地転用という許可を得る必要があるためです。
中でも優良な農地として指定されている土地は、転用が認められないことが多く、土地活用の大きな壁となっています。ここでは、農地転用の基本的な内容から、日本の農地事情、転用に制限がある理由までを解説します。
農地転用の概要
「農地転用」とは、農地を宅地や道路など、農地以外の用途へと変更することを指します。農地を別の用途に転用する際は、農地法に基づく厳格な規制があり、日本の農業生産力を維持するために慎重な手続きが必要となります。
そのため、農地転用を計画する際は自己判断で進めることはできず、事前に土地の区分や規制の内容、必要な許可申請などについて十分な調査と準備が必要です。
年々減少する日本の農地面積
年々減少する日本の農作物を育てるための土地は、令和6年7月時点で427万2,000ha(ヘクタール)です。これは前年より2万6,000ha減少しており、農作物の収穫量や食料自給率の低下にもつながっています。
そのため、日本は食料の多くを海外からの輸入に依存する状況となっているため、食料の安定供給を確保するために農地法で農地は保護されています。
農地転用を自由にできない理由
農地転用には農地法による厳格な規制があり、自由な売買は認められていません。これは国土が狭い日本において、食料自給率を維持するために農地を保護する必要があるためです。
農地法では、農地の売買や貸借には農業委員会の許可が必要となり、農地を宅地などへ転用する場合は都道府県知事や市町村長の許可が求められます。また、農地を転用目的で売買・貸借する際にも同様の許可が必要です。
農地転用できない土地の種類

農地転用の許可を得るためには、その土地がどのような区分に該当するのかを把握する必要があります。特に、農業振興地域に指定されている農用地区域や、優良な農地として保護されている甲種農地、第1種農地は、原則として転用が認められません。
ここでは、転用が認められない土地の種類とそれぞれの特徴について詳しく解説します。
農用地区域
農用地区域は、日本の食料生産において特に重要な役割を果たす農地を指します。具体的には、広大な土地に集団的にまとまっている農地や、土地改良事業によって整備された生産性の高い農地などが該当します。
このような農用地区域に指定された農地は、食料生産の基盤として保護する必要があるため、原則として農地転用は認められません。ただし、公共施設の建設など、真にやむを得ない場合や、農業振興地域整備計画の変更が認められる特別な事情がある場合に限り、農用地区域から除外される可能性があります。
甲種農地
甲種農地は、市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地です。大型の農業機械による効率的な耕作が可能で、農業生産性が極めて高い土地であるため、農地転用は原則として認められません。
ただし、農業用施設や農産物の加工・販売施設の建設、また周辺に適切な代替地がない場合の集落に接続する住宅建設など、限られた条件下では例外的に転用が許可される場合があります。
第1種農地
第1種農地は、集団的にまとまって存在し、農業公共投資の対象となるなど、高い生産力を持つ優良な農地です。こうした農地は国内の食料生産に重要な役割を果たすため、農地転用は原則として許可されません。
ただし、農業用施設の建設や、周辺に適切な代替地がない場合の住宅建設など、特定の条件下では例外的に転用が認められることがあります。
農地転用できる土地の種類

農地転用が認められない土地がある一方で、一定の条件を満たせば転用が可能な土地も存在します。第2種農地や第3種農地は、周辺の状況や立地条件によって、転用の許可が下りる可能性があります。
ここでは、転用の可能性がある土地の種類と、それぞれの転用条件について詳しく解説します。
第2種農地
第2種農地は、小集団の生産性の低い農地で農用白地地域や農業振興地域外に位置し、第3種農地に近接している区域、または将来的に市街化が見込まれる区域の農地を指します。また、10ヘクタール未満の小規模な集団農地も第2種農地に該当します。
農地から500m圏内に公共交通機関や公共施設がある場合も該当します。第2種農地の転用については、周辺に代替地がない場合に限り許可されます。
第3種農地
第3種農地は、市街化が進んでいる区域内の農地を指し、農用白地地域や農業振興地域外の農地が該当します。前面道路に上下水道やガス管が2種類以上埋設され、500m圏内に複数の公共施設がある農地や、300m圏内に公共交通機関などがある農地が含まれます。
また、宅地化率が40%以上の区画内や用途地域が定められている区域内の農地も第3種農地とされており、基準を満たせば農地転用が認められます。
条件を満たせば転用できる可能性がある土地
第1種農地と甲種農地は、原則として農地転用が制限されていますが、特定の条件下では転用が認められます。いずれも500平方メートル以内の集落接続の住宅の建設など、用途や目的によって転用が可能となり、地域の実情に応じた土地利用が認められています。
農地転用できるかどうかの2つの認可基準

農地転用の許可を得るためには、立地基準と一般基準という2つの基準を満たす必要があります。これらの基準は、農地の区分や周辺環境、転用目的など、さまざまな観点から審査されるため、基準を満たさない場合は転用が認められません。
ここでは、農地転用の許可に必要な2つの基準について詳しく解説します。
立地基準
立地基準は、土地の営農状況や市街地との関係性から農地転用の可否を決める基準で、以下5つに分類されます。
- 農用地区域内農地:市町村が農振法に基づいて農業振興地域整備計画で定めた区域内の農地
- 甲種農地:市街化調整区域内の10ヘクタール以上の規模で、土地改良事業完了後8年以内の効率的な農作業が可能な農地
- 第1種農地:10ヘクタール以上の集団的な農地や特定土地改良事業区域内の農地
- 第3種農地:市役所から300m以内や宅地化率40%超の市街化が進んだ区域の農地
- 第2種農地:市役所から500m以内や10ヘクタール未満の宅地化が見込まれる区域の農地、または他の区分に該当しない農地
農用地区域では転用が不許可となり、第1種農地と甲種農地も原則として転用できません。
一方、第3種農地と市街化区域内の農地は原則として転用が許可されます。第2種農地については、第3種農地への立地が困難な場合にのみ転用が認められます。
一般基準
一般基準は、農地転用を審査する際の基本的な判断基準として定められています。この基準では、申請者の資金力や事業の実行可能性、転用面積の妥当性などが総合的に評価されます。
具体的には、申請者が農地転用後の事業に必要な資金を有しているかや、許可後に速やかに事業を開始できるのかなどを確認します。また、周辺の農地への影響も重要な審査項目となり、転用によって隣接する農地での営農活動に支障をきたさないことが求められます。
農地転用できない土地の4つの活用方法

農地転用の許可が下りない土地を所有していると、有効活用の方法が見つからず、固定資産税だけが負担となるでしょう。しかし、転用ができない土地であっても、行政機関への相談や農家への売買、市民農園の運営など、いくつかの活用方法が存在します。
ここでは、転用できない農地の具体的な活用方法を4つ紹介します。
行政機関に相談して売買する
農用地区域(青地)の農地を売却や賃貸したい場合、農業委員会の「農地移動適正化あっせん事業」の活用を検討してみましょう。このあっせん事業では、農地の売却価格はあっせん委員会が決定しますが、農家の方にとって大きなメリットがあります。
特に、譲渡所得税について800万円もの特別控除を受けられるため、税負担を大幅に軽減できます。このように、行政機関による仲介制度を利用することで、農地の移転をスムーズに進められるだけではなく、税金面でもメリットがあります。
農家に貸す・売る
農地の賃貸や売却を考える際、もし借り手や買い手となる農家がいる場合は、農地のままでの取引が可能です。ただし、このような取引には必ず農業委員会の許可が必要となるため、事前に申請手続きを済ませておく必要があります。
具体的な流れとしては、まず農業委員会へ申請を行い、許可を取得してから賃貸契約や売買契約の締結へと進みます。
市民農園を運営する
農地を市民農園として活用する場合、市民農園整備促進法、特定農地貸付法を守らなくてはいけません。市民農園整備促進法では、指定区域や市街化区域内の農地が対象となり、休憩施設やトイレなどの設置が必要となりますが、市町村への申請で認定が可能です。
一方、特定農地貸付法では、農業委員会の承認が必要となります。また、農園での農業経営は農家が行い、住民等が農園で農作業を行う農園利用方式もあります。法的手続きは不要ですが、開設者と利用者とで「農園利用契約」を締結する必要があります。
農地バンクに登録する
農地集積バンク(農地バンク)は、地方公共団体が運営する農地中間管理機構による貸し借りの仲介システムです。このシステムを利用すると、自分で借り手を探す手間が省けるだけではなく、賃借料が確実に振り込まれ、農地の適切な管理も期待できます。
さらに、貸付期間が終了すれば農地は確実に返却され、税金面でも優遇措置が適用されるなど、農地所有者にとって安心できる仕組みとなっています。特に、農地転用が難しい土地の有効活用を考える際には、農地バンクへの登録は有力な選択肢の一つになるでしょう。
農地転用の手続き方法

農地転用の条件を満たしていても、正しい手続きを行わなければ許可を得ることはできません。申請には多くの書類が必要となり、準備に時間がかかることもあります。
また、申請後に書類の不備を指摘されると、手続きが大幅に遅れてしまう可能性もあります。ここでは、農地転用の具体的な申請方法から、必要な書類の種類、申請が免除される条件までを解説します。
農地転用の許可を申請する
農地転用の許可申請は、農地の面積と区域によって手続きが異なります。4ha以下の場合は農業委員会への申請から始まり、委員会が知事や市町村長の許可が必要です。
一方、4ha以上の場合は農林水産大臣の許可が必要となりますが、申請は同じく農業委員会へ提出します。また、市街化区域内の農地では、生産緑地指定がない限り許可申請は不要ですが、転用前に農業委員会への届出が必要です。
必要な書類を用意する
農地転用の申請手続きでは、全部登記事項証明書と土地の位置を示す地図の提出が基本となります。また、その農地が賃貸借の対象となっている場合、特に事業用地として貸し出す際には、都道府県知事などによる許可証明書も必要です。
ただし、転用の目的や状況によって必要書類は変わってくるため、漏れのない申請を行うためにも、事前に農業委員会へ相談することをおすすめします。
申請免除の条件を確認する
農地転用の申請が免除される場合として、国や都道府県による転用、土地収用法に基づく転用、農業経営基盤強化促進法による転用、そして市町村が土地収用法の対象事業のために行う転用などが定められています。
これらはいずれも高い公共性を持つ事業として認められているため、通常の許可申請手続きは不要です。ただし、自身の転用計画がこれらの免除条件に該当するかどうか判断が難しい場合には、農業委員会に確認することで、不要な手続きや手続き漏れを防ぐことができます。
まとめ|農地転用できない土地でも工夫次第で有効活用できる

この記事では、農地転用の基本的な内容から、転用できない土地の種類、認可基準、活用方法まで詳しく解説しました。
農地転用ができない土地には、農用地区域や甲種農地、第1種農地があり、これらは高い農業生産性や優良な営農条件を持つ土地として保護されています。一方で、第2種農地や第3種農地は、立地基準と一般基準を満たすことで転用が可能です。
農地転用ができない場合でも、行政機関への相談や農家への売買・賃貸、市民農園の運営、農地バンクへの登録など、土地を有効活用する方法があります。転用の手続きには許可申請が必要ですが、条件によっては申請が免除されるケースもあります。正しい知識を持ち、適切な方法で農地を活用しましょう。
注文住宅の土地選び・資金計画に
お悩みはありませんか?
「ウチつく」オンライン無料相談なら
プロが徹底サポート!
-
家づくりの準備がワンストップで整う
段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。
-
住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける
専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。
-
最短1時間・オンラインで気軽に相談できる
スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。
ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで
幅広いラインアップ
ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!
参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象


Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!


Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!
納得・安心の家づくりなら
「ウチつく」にお任せください!
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事