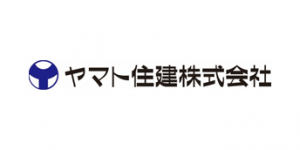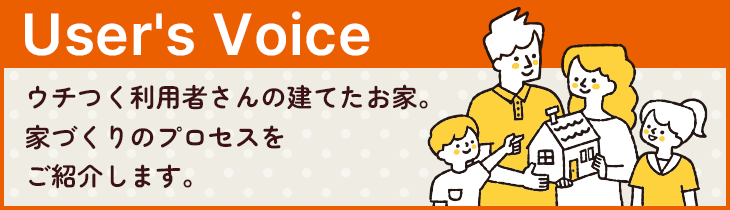ローコスト住宅がやばいと言われる理由は?安くなる仕組みからメリットまで解説

住宅購入を検討する中で「ローコスト住宅はやばい」とマイナスのイメージを持っている声を耳にする機会が増えています。
確かに、通常の注文住宅に比べて価格を大幅に抑えられるローコスト住宅には、間取りの自由度が低い、設備の品質に不安がある、メンテナンス費用が予想以上にかかるなど、いくつかの懸念点があります。
しかし、コストを抑える仕組みを理解し適切な選び方をすれば、ローコスト住宅は新生活を無理なく始められる魅力的な選択肢の1つです。
この記事ではローコスト住宅がやばいと言われる理由から値段が安くなる仕組み、そして失敗しないための選び方のポイントまでを詳しく解説します。記事を読んで、より良い住まい選びへのきっかけにしてみましょう。
目次
ローコスト住宅がやばいと言われる6つの理由

ローコスト住宅には「やばい」と言われるほどの問題点があると指摘する声が多く上がっています。確かに価格を抑えるためにさまざまな制限や制約があり、実際に住んでからも予想外の費用がかかるケースもあります。
ここでは、ローコスト住宅のデメリットとして挙げられる6つの理由を詳しく解説します。
自由に間取りが選べない
ローコスト住宅では建築コストを抑えるため間取りやデザイン、設備の自由度が制限されます。例えば、凹凸の多い間取りは工事費用が増加するため、多くの場合はシンプルな四角形のプランに限定されます。
規格化された設計で効率的な施工を実現する一方で、各家庭の生活スタイルや好みに応じたカスタマイズは困難です。そのため、間取りや設備にこだわりの強い方にとっては、思い描いた理想の住まいを実現することが難しくなるでしょう。
修理やメンテナンス費用が膨らむ
ローコスト住宅は耐久性が低めに設定されているため、定期的なメンテナンスにかかる費用が予想以上に高額になることがあります。例えば、雨漏り対策のための屋根や外壁の塗り替え、シロアリ対策としての床下薬剤散布、水まわり設備の取り替えなど、さまざまな箇所でメンテナンスが必要です。
当初は購入費用を抑えられても、長期的に見ると修繕やメンテナンスの頻度が増えることで、一般的な注文住宅や建売住宅と同程度の費用がかかってしまう可能性があります。
標準設備の質が低くなる
ローコスト住宅では建築費用を抑えるため、標準設備のグレードが低めに設定されています。例えば、キッチンやお風呂などの水まわり設備は、機能が限定的な基本モデルが採用されることが多いです。
高性能な設備に比べると使い勝手が悪く、デザイン性にも物足りなさを感じることがあります。毎日使用する設備だけに、グレードの低さは日常生活の快適さに大きく影響を与えてしまうため、設備の質にこだわりたい方には不向きな選択肢といえるでしょう。
冷暖房費が予想以上にかかる
ローコスト住宅は、建築コストを抑えるため低グレードの断熱材を使用することが多く、これにより気密性が十分に確保できない傾向にあります。薄い断熱材は壁や天井、床との間に隙間ができやすく、外気の影響を受けやすい住環境となってしまうのです。
その結果、夏場は室内が暑くなり、冬場は寒さが厳しくなります。さらに、冷暖房の効きも悪くなるため、光熱費が予想以上にかさむことになります。
建物の寿命が短くなる
建物の寿命が短くなる原因は、耐久性・耐火性・耐震性の低さにあります。もちろんローコスト住宅も建築基準法に沿って建てられていますが、費用を抑えるために基準を最低限満たすレベルの建材が使われることが多いです。
そのため、建物への負荷が大きい雨風や地震、火災などに対する耐性が弱く、高性能住宅と比べて寿命が短くなります。特に地震が多い日本では、耐久性・耐火性・耐震性の低い住宅は災害時に大きな被害を受けるリスクがあるため、注意が必要になります。
オプション費用が想定外に増える可能性がある
オプション費用が想定外に増える可能性があるのは、ローコスト住宅の制限された基本プランに追加要望を出すためです。間取りや設備を購入者の希望に合わせるオプションは用意されていますが、規格外のものを選ぶと費用が大幅に上がり、一般の注文住宅より高額になることもあります。
ローコスト住宅の費用相場

ローコスト住宅は一般的に坪単価30万円から50万円程度で、注文住宅の70万円から80万円と比べて大幅に安く設定されています。
例えば30坪の住宅を建てる場合、ローコスト住宅なら900万円から1,500万円程度で建築できますが、注文住宅では2,100万円から2,400万円ほどの費用がかかります。このように同じ広さでも坪単価の違いで建築費用に大きな差が生まれるのです。
ただし、これらの費用はあくまでも建築費用のみの金額であり、土地代や諸費用は別途必要になるため、予算を立てる際は注意が必要です。
ローコスト住宅の値段が安くなる仕組み

ローコスト住宅は、通常の注文住宅に比べて大幅に価格を抑えることができます。しかし「安いのにはそれなりの理由がある」と不安を抱く方も多いのではないでしょうか。
ここでは、ローコスト住宅の価格が安くなる仕組みを詳しく解説します。
建材の大量仕入れでコストを抑える
大量仕入れによる建材のコスト削減は、ローコスト住宅の特徴の一つです。間取りや設備のカスタマイズ性を制限することで、複数の住宅に同じ建材を使用できるようになり、まとめて仕入れることが可能です。
建材の大量購入は単価の引き下げにつながり、建材コストを一般的な注文住宅の半分以下に抑えられることもあります。
間取りを工夫して建築費を削減する
ローコスト住宅では、間取りの制限が建築費削減の重要な要素となっています。一般的な注文住宅のように自由に間取りを決められるのではなく、あらかじめ用意された規格プランの中から選ぶ形式を採用することで、施工の効率化とコスト削減を実現しています。
例えば、キッチンやバスルームの配置を固定したり、壁の位置を規格化したりすることで、設計費用や施工期間を大幅に短縮し、結果として建築費を抑えることができるのです。
施工の効率化で人件費を節約する
ローコスト住宅の建築費削減において、施工の効率化による人件費の節約は大きな要因となっています。規格化された間取りと建材を使用することで、高度な技術を必要とする作業が少なくなり、経験の浅い職人でも施工ができるようになります。
また、作業手順が標準化されているため、工期を短縮できることも人件費削減につながっているのです。
地域を絞って広告費をかけることで経費を削減する
広告費の削減もローコスト住宅の価格を抑える重要な要素です。大手ハウスメーカーは全国規模のテレビCMやWeb広告など、大規模な宣伝活動を展開するため、その費用は住宅価格に反映されます。
一方でローコスト住宅を手がける会社は、特定のエリアに絞った地域密着型の宣伝を主体とするため、広告費を大幅に抑えることができます。チラシやローカル番組でのCM、地域限定のWeb広告など、効率的な宣伝方法を選ぶことで、経費削減を実現しているのです。
ローコスト住宅のメリット

ローコスト住宅には、品質や耐久性に関するさまざまな懸念点があります。しかし、それらのデメリットばかりに目を向けていると、ローコスト住宅が持つ大きな可能性を見逃してしまうかもしれません。建築費を抑えられることは、新生活の充実につながるだけではありません。
入居までのスピードや将来的な建て替えも視野に入れた住まい方も可能です。ここでは、ローコスト住宅ならではのメリットを解説します。
建築費を抑えて新生活を充実させる
建築費が抑えられることはローコスト住宅の大きなメリットで、余った予算を新生活に向けた家具や家電の購入に活用できます。例えば、キッチンに最新の冷蔵庫を設置したり、リビングに快適なソファを置いたり、寝室にゆとりのある収納家具を取り入れたりと、暮らしの質を高める選択が可能になります。
比較的早く新居に住める
ローコスト住宅は、注文から完成までの期間が一般的な注文住宅の半分程度で済むため、早期の入居が可能です。通常の注文住宅では完成まで半年ほどを要しますが、ローコスト住宅なら3ヶ月ほどで完成します。この短い工期は、賃貸住宅の更新時期に合わせた引っ越しや、出産前の住まいの確保、子どもの新学期に合わせた転居など、時期を考慮して入居を計画している方にとって大きなメリットとなるでしょう。
ライフステージに合わせて建て替えできる
ライフステージに合わせた住宅の建て替えは、ローコスト住宅ならではの大きなメリットと言えます。建築費用が抑えられることで住宅ローンの返済負担が軽くなり、将来的な建て替えの資金計画が立てやすくなるためです。
たとえば子どもの独立で不要になった子ども部屋を趣味の部屋に変えたい時や、年齢とともにバリアフリー化が必要になった時なども、その時々の家族のニーズに合わせて住まいを最適化できます。
ローコスト住宅で失敗しない選び方のポイント

ローコスト住宅は、価格の安さと引き換えにいくつかのリスクを抱えています。しかし、適切な選び方をすることで、これらのリスクを最小限に抑えることができます。
ここでは、ローコスト住宅選びで失敗しないための具体的なポイントを紹介します。
モデルハウスで実際の暮らしをイメージする
ローコスト住宅の見学会やモデルハウスは、これからの暮らしをより具体的にイメージできる貴重な機会となります。写真や図面だけでは把握しづらい、部屋の広さや収納力、窓からの採光具合、設備の使い勝手なども、実際に見て触れることで正確に理解できるためです。
特に規格住宅の場合、展示されている建物と実際に建てる住宅の仕様がほぼ同じになるため、キッチンでの動線や寝室の快適性など、日常生活での使い心地を細部まで確認することができます。
複数のハウスメーカーの特徴を比べてみる
ローコスト住宅のハウスメーカー選びは、将来の暮らしを左右する重要な決断となります。建築費用が安くても施工品質が悪かったり、アフターサービスが行き届いていなかったりと、会社によって提供されるサービスの内容は大きく異なるためです。
少なくとも2社以上のハウスメーカーを比較検討し、実際の施工事例や標準仕様書、保証内容、アフターフォローの体制などを詳しく確認することをおすすめします。また、担当者との面談時には具体的な質問を投げかけ、対応の丁寧さや提案力なども含めて総合的に判断することが賢明です。
災害に強い家かどうかチェックする
自然災害の多い日本において、ローコスト住宅の構造強度の確認は欠かせない重要なポイントとなります。コストを抑えるために建築基準法の最低基準を満たす程度の材料が使用され、耐震性や耐火性、耐久性が十分でないケースもあるためです。
構造材の品質や耐震等級、制震・免震設備の有無、基礎や地盤の補強方法など、災害への備えに関する情報はハウスメーカーの資料やホームページで詳しく確認できます。地震や台風、豪雨といった自然災害から家族の安全を守るため、建物の強度や災害対策は慎重に検討する必要があります。
追加費用を確認する
ローコスト住宅の実際の費用は、広告に表示された本体工事費だけではないことを理解しておく必要があります。外壁や屋根、内装の仕上げ材、照明器具やエアコンなどの設備機器は別途オプション費用がかかることが多く、当初の予算をはるかに超えてしまうケースもあるためです。
さらに、地盤調査や地盤改良、浄化槽の設置といった工事費用も追加で必要になる可能性があります。加えて、建材のグレードを抑えているため、将来的な修繕やメンテナンス費用が割高になる傾向もみられます。
断熱性にこだわる
快適な住まいづくりにおいて、ローコスト住宅の断熱性能は特に注意が必要な要素となります。グレードの低い断熱材を使用すると、夏場は室内に熱がこもりやすく、冬場は暖かい空気が逃げやすくなるため、年間を通じて空調効率が極めて悪くなるためです。
また、断熱材は温度管理だけでなく、外部の騒音を遮断する防音性や、結露を防ぐ気密性にも大きく関わってきます。そのため、イニシャルコストは上がりますが、断熱等級の高い断熱材を選ぶことで、光熱費の削減や快適な室内環境の実現につながり、長期的には家計にもやさしい住まいとなるでしょう。
購入後のサポート内容を確認する
ローコスト住宅におけるアフターサポートの確認は、快適な暮らしを長く続けるための重要なポイントとなります。一般的に低価格の住宅は、設備の経年劣化が早く、外壁の塗り替えや防水工事といったメンテナンスの頻度が高くなる傾向にあるためです。
そこで、建物の保証期間や保証範囲、定期点検の実施回数、修繕やリフォームの相談体制、緊急時の対応窓口など、購入後のサポート内容を事前に詳しく確認することが大切です。特に、地域にメンテナンス対応の拠点があるかどうかも、スムーズなアフターケアを受けられるかどうかの重要な判断材料となります。
まとめ|ローコスト住宅のメリットを理解して選択肢を広げよう

この記事では、ローコスト住宅が「やばい」と言われる理由について、間取りの制限や将来的な費用負担など、具体的な課題を解説しました。一方で、建材の大量仕入れや施工の効率化によって価格を抑える仕組みも明らかにしました。
確かにローコスト住宅には、標準設備の質や建物の寿命など、いくつかの懸念点があります。しかし、建築費を抑えられ、比較的早く入居できるなどのメリットも存在します。
ローコスト住宅を選ぶ際は、モデルハウスでの確認や複数のハウスメーカーの比較、断熱性能の確認など、慎重に検討することが大切です。また、追加費用や購入後のサポート内容まで確認することで、将来的な不安を解消できます。
ローコスト住宅のメリットやデメリットを理解した上で、あなたのライフプランに合った住まい選びをしましょう。
注文住宅の土地選び・資金計画に
お悩みはありませんか?
「ウチつく」オンライン無料相談なら
プロが徹底サポート!
-
家づくりの準備がワンストップで整う
段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。
-
住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける
専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。
-
最短1時間・オンラインで気軽に相談できる
スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。
ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで
幅広いラインアップ
ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!
参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象


Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!


Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!
納得・安心の家づくりなら
「ウチつく」にお任せください!
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事