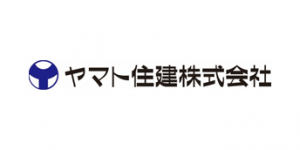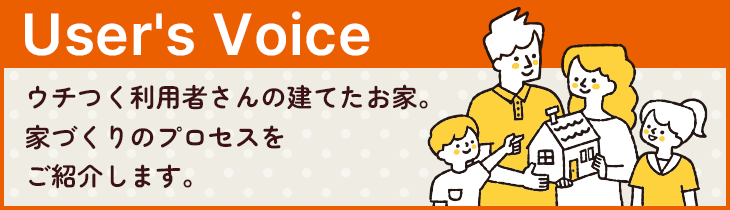隠し部屋を作りたい場合の使用例とは?安く抑えるポイントも解説

隠し部屋を作りたいと考えている方も多いのではないでしょうか。隠し部屋は、趣味に没頭できるプライベート空間や仕事に集中できるワークスペース、生活を便利にする収納エリアとしても活用できます。しかし、建築費用が高額になりがちなため、予算内で理想の空間を実現するには、事前の計画が欠かせません。
この記事では、隠し部屋のさまざまな使用例から、費用を抑えるためのポイント、さらには建築時の注意点まで詳しく解説します。隠し部屋作りの第一歩として、基本的な知識を身につけましょう。
隠し部屋を作りたい場合の使用例

隠し部屋は用途に応じてさまざまな使い方ができ、生活をより豊かにする可能性を持っています。書斎やワークスペース、収納エリアとしての活用はもちろん、趣味に没頭できる特別な空間としても人気があります。
ここでは、隠し部屋の具体的な使用例を見ていきましょう。
読書に没頭できる書斎
隠し部屋を書斎として活用する場合、静かで落ち着いた雰囲気づくりが大切になります。1人用のコンパクトなデスクと椅子を配置することで、集中して読書や勉強ができる空間を実現できます。
壁一面に本棚を設置すれば、自分だけのミニ図書館として活用することもできるため、読書好きの方に特におすすめの使い方といえるでしょう。直射日光が入りにくい環境は本の劣化を防ぐメリットがありますが、大量の本を置く場合は床の耐荷重を確認し、必要に応じて補強工事を検討する必要があります。
仕事に集中できるワークスペース
隠し部屋をワークスペースとして活用することで、仕事とプライベートの切り替えがスムーズになります。在宅ワークが増えている現代では、パソコンやWi-Fiなどの通信環境を整えた専用の作業スペースがあると効率的に仕事を進められます。
壁にホワイトボードを設置してアイデアを書き留めたり、快適な照明で目の負担を減らしたりすることもおすすめです。インターホンや電話の配線を通しておけば、急な来客や緊急の連絡にも対応できる実用的な仕事部屋として活用できます。
生活を便利にする収納エリア
隠し部屋を収納エリアとして活用すれば、家全体がすっきりと片付いた印象になります。特に納戸として使う場合は、季節家電やレジャー用品など、普段使わないものを効率的に保管できるため、リビングや寝室の収納スペースに余裕が生まれます。
ハンガーポールと棚を設置してウォークインクローゼットにするのも人気の使い方で、衣類や小物を整理しやすい収納空間を実現できるでしょう。
趣味を満喫するシアタールームや音楽室
隠し部屋を趣味の空間として活用するなら、シアタールームや音楽室にするのも良いでしょう。防音壁や防音床、防音扉を設置することで、生活音を気にせず映画鑑賞や楽器演奏を楽しめる環境が整います。
遮音性や吸音性を高めた専用の空間があれば、リラックスしながら趣味に没頭できる贅沢な時間を過ごせるでしょう。
非常時に役立つセーフティルーム
隠し部屋をセーフティルームとして整備すれば、不測の事態に備えた安全な避難場所になります。隠し扉をつくり、不法侵入者から見つかりにくい設計にすることで、家族の安全を確保できます。
防犯カメラのモニターを設置すれば室内から侵入者の動きを把握でき、より安心な避難場所として機能するでしょう。
注文住宅で隠し部屋を作る際のアイデア

注文住宅で隠し部屋を作る場合、どのような工夫ができるのか気になる方も多いのではないでしょうか。実は、既存の扉や建具を利用したり、普段は見落としがちな階段下や屋根裏を活用したりすることで、コストを抑えながら隠し部屋を実現できます。
ここでは、注文住宅で隠し部屋を作るための具体的なアイデアを紹介します。
扉で隠す
隠し部屋への入口は、本棚や壁面などの日常的なインテリアに上手く組み込むことで存在を隠すことができます。本棚タイプの扉は、棚板がドアノブの代わりとなり、重い本棚が開くとは想像しにくいため人気があります。ただし、実際の本を収納すると開閉が重くなるため、フェイクの本を使用して軽量化する工夫も効果的です。
アートや壁面の装飾を利用した隠し扉も、洗練された選択肢となります。大きな額縁の裏側に扉を設置したり、木格子などの縦ラインで壁面を統一的にデザインしたりすることで、扉の存在を巧妙に隠すことができます。
さらに、畳や床板を活用した床下収納タイプの隠し扉も、日本家屋ならではの趣のある選択肢です。隠し扉を設置すれば、地下室やワインセラーなどへの階段を隠すことができます。
階段下や屋根裏を活用する
家の構造を上手く利用すれば、デッドスペースを魅力的な隠し部屋へと変えることができます。階段下のスペースは、斜めに切り取られた独特の形状を活かして収納や書斎として活用できます。
また、屋根裏は天井高や床面積に余裕があれば、子どもの秘密基地や趣味の部屋として理想的な空間になるでしょう。普段は目に触れないこれらの場所を有効活用することで、隠れた魅力的なスペースを作ることが可能です。
多目的な利用を考えておく
隠し部屋の設計では、将来的な用途の変更にも対応できる柔軟な空間づくりが重要になります。基本的な設備として電源や照明、通信環境を整えておけば、書斎やワークスペースとしての利用が可能です。
さらに防音設備を追加すればホームシアターや音楽室として、収納棚を設置すれば趣味の道具や季節物の収納スペースとして活用できます。このように、あらかじめ多目的な利用を想定した設計をしておくことで、ライフスタイルの変化に応じて柔軟に部屋の使い方を変えることができます。
隠し部屋を作る際の5つの注意点

隠し部屋を作る際には、いくつか気を付けるべきポイントがあります。違法にならないように注意することや建築費用の増加、さらには使い勝手や広さ、照明や換気の設備など、事前に確認しておくべき重要な要素がたくさんあります。
ここでは、隠し部屋を作る際に注意すべき5つのポイントを見ていきましょう。
違法にならないように注意する
隠し部屋を設置する際は、建築基準法に基づいた適切な申告と手続きが不可欠です。入口が巧妙に隠されていても、建築確認申請時の図面には正確な位置や寸法を明記する必要があります。
面積や天井高などの情報を意図的に隠したり、申告を怠ったりすると違法建築とみなされ、重大な問題に発展する可能性があります。そのため、隠し部屋の計画段階から建築の専門家に相談し、法令に準拠した設計と施工を依頼しましょう。
建築費用が高くなる
隠し部屋の設置は機能性や使い方によって建築費用が大きく変動します。最もシンプルな本棚スライド式の扉でも、オーダーメイドの造作家具として10万円から20万円程度の費用が必要です。ウォークインクローゼットとして活用する場合は収納設備の規模によって15万円から100万円程度、音楽室やシアタールーム用の防音設備を設置すると200万円から450万円程度まで費用が上がります。
特に地下に隠し部屋を設ける場合は、1坪あたり50万円から200万円と高額な費用が必要になるため、慎重な計画が求められます。費用は素材の選定や施工会社によっても変わるため、予算と相談しながら優先順位をつけて、実現可能な隠し部屋の設計を進めることが大切です。
使いやすさを重視する
隠し部屋の魅力を最大限に引き出すには、日常的な使いやすさを重視しましょう。重すぎる扉や複雑な開閉は、当初の楽しみが薄れて次第に使用頻度が低下し、貴重なスペースが無駄になってしまう可能性があります。
特に屋根裏を活用する場合は天井高が1.4m程度と限られるため、身体的な負担が大きく、収納や居室としての機能性も制限されます。隠し部屋の設計では、実用性を考え、長期的な視点で快適に利用できる工夫を取り入れることが重要です。
照明や換気に気を付ける
隠し部屋を快適な空間として活用するには、適切な照明計画と換気システムの設置が重要なポイントとなります。窓を設けにくい構造上の特徴から、LEDダウンライトや間接照明などを効果的に配置し、目的に応じた明るさを確保する必要があります。
また、空気が滞留しやすい密閉空間では、居室でなくても個別の換気扇を設置することで結露やカビの発生を防ぎ、空調設備と組み合わせることで年間を通じて快適な室内環境を維持することができるでしょう。
用途に合わせた広さを確保する
隠し部屋の広さは用途に応じて柔軟に検討する必要があります。最小限の書斎として使用する場合は1畳程度のスペースで十分ですが、より広い空間が必要な用途には適していません。設置場所によって天井高や広さに制限が生じることもあるため、計画段階での確認が重要です。
隠し部屋の費用を安く抑えるポイント

隠し部屋は、費用がかかるというイメージがあるかもしれません。しかし、既存の空間を活用したり、間取りをシンプルにしたりすることで、実は費用を抑えることができます。
ここでは、隠し部屋を作る際の費用を抑えるためのポイントを紹介します。
元々ある空間を活用する
既存の空間を活用することで、隠し部屋を低予算で設置できます。元々ある納戸や階段下のデッドスペース、使用頻度の低い部屋などを改装し、本棚や壁紙で扉を隠すことで、隠し部屋として生まれ変わらせることができます。
住宅の構造を変更する必要がないため、大掛かりな工事も不要です。たとえば階段下の収納扉を本棚と一体化させたりすることで、スタイリッシュな隠し部屋を実現できるため、予算を抑えながらも理想的な空間づくりが可能になります。
シンプルな間取りにする
隠し部屋の間取りは、シンプルに作ることで費用を抑えることができます。複雑な間取りは魅力的に見えるかもしれませんが、通路を迷路のように長く設計したり、隠し部屋の中にさらに隠し部屋を設けたりすると、必要な資材や工事の手間が大幅に増加します。
たとえば、長い通路を作るには壁材やフローリング材が余分に必要となり、二重の隠し部屋では扉の設置工事も2回必要になるため、予算が膨らむ原因です。そのため、書斎やプライベートルームとして使用する場合は、入り口から直接アクセスできるシンプルな一室構造にすることをおすすめします。
まとめ|隠し部屋を作る際は事前にしっかりと計画を立てよう

この記事では、隠し部屋の具体的な使用例から費用を抑えるポイントまでを詳しく解説しました。隠し部屋は書斎やワークスペース、収納エリア、シアタールームなど、さまざまな用途で活用できます。作り方も、扉で隠す方法や階段下の空間を利用する方法など、複数の選択肢があります。
ただし、作る際は建築基準法に違反しないよう注意が必要です。また、照明や換気、広さなど、快適に過ごすための要素も重要になります。費用面では、元々ある空間を活用したり、シンプルな間取りにしたりすることで、予算を抑えることが可能です。
隠し部屋を作る際は、用途や予算、建築上の制限などを踏まえて、しっかりと計画を立てましょう。綿密な計画があれば、快適で魅力的な隠し部屋を実現できます。理想の隠し部屋作りに向けて、この記事で紹介したポイントを参考にしてください。
注文住宅の土地選び・資金計画に
お悩みはありませんか?
「ウチつく」オンライン無料相談なら
プロが徹底サポート!
-
家づくりの準備がワンストップで整う
段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。
-
住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける
専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。
-
最短1時間・オンラインで気軽に相談できる
スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。
ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで
幅広いラインアップ
ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!
参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象


Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!


Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!
納得・安心の家づくりなら
「ウチつく」にお任せください!
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事