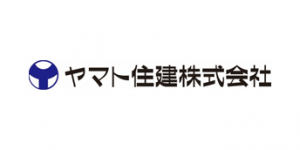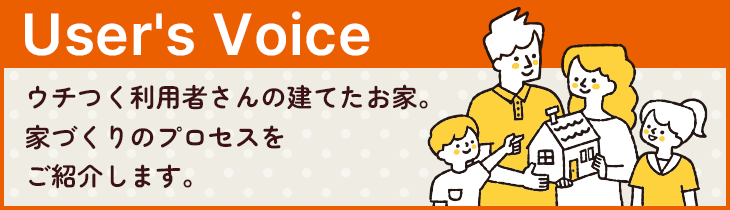ハザードマップの見方がわかる!確認する方法や知っておきたい情報を紹介

近年、日本各地で大規模な自然災害が増加しており、土地選びや住宅購入の際にハザードマップの確認が欠かせなくなっています。しかし、ハザードマップには洪水や土砂災害、地震など、さまざまな種類があり、見方がわからないと感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ハザードマップの基本的な見方から、オンラインでの確認方法、そして災害リスクの具体的な把握方法まで、詳しく解説します。これらの知識を活用することで、安全な土地選びや、必要な防災対策ができます。
目次
ハザードマップとは

ハザードマップとは、台風や地震、洪水といった自然災害による被害を予測し、その影響範囲や避難経路をわかりやすく示した地図のことを指します。
各自治体が作成するこの地図には、土砂災害の危険区域や浸水が予想される地域、避難所の位置などが色分けされて表示されており、住民の迅速な避難行動をサポートします。近年、気候変動の影響で自然災害が激甚化する中、被害の軽減や防災意識の向上に欠かせないツールです。
また、不動産購入の際にも、物件周辺の災害リスクを確認するための重要な判断材料となるため、多くの方が活用しています。
ハザードマップの種類

ハザードマップには、自然災害の種類によってさまざまな種類があり、それぞれの見方や注意点が異なります。洪水や津波、土砂災害など、地域によって想定される災害は大きく異なるため、自分の住む地域に関係するハザードマップを正しく理解することが重要です。
ここでは、各種ハザードマップの特徴や見方のポイントを詳しく解説します。
洪水に関するハザードマップ
洪水ハザードマップは、台風や集中豪雨による河川の氾濫や堤防の決壊時に想定される浸水範囲と深さを示した防災地図です。また、避難所の位置や安全な避難経路なども明記されているため、地域の水害リスクを事前に把握できます。
特に、近年の豪雨災害の激甚化を受けて、各自治体では従来の想定を上回る規模の降雨にも対応した新しいハザードマップを作成し、住民の防災意識向上に努めています。
内水に関するハザードマップ
内水ハザードマップは、下水道や排水設備の処理能力を超えた大雨により発生する浸水被害の防災地図です。特に都市部では、アスファルトやコンクリートで地面が覆われているため、雨水が地中に浸透せず、下水道に一気に流れ込むことで浸水が起きやすくなります。
内水ハザードマップでは、過去の浸水実績や地形の特徴から、道路冠水や地下施設への浸水が予想される区域が色分けされており、避難所の場所も明示されています。
高潮に関するハザードマップ
高潮ハザードマップは、台風や低気圧による異常な海面上昇で起こる浸水被害を予測した防災地図です。特に台風の強風で海水が沿岸に吹き寄せられ、気圧低下と重なると海面が大きく上昇し、堤防を超えて沿岸部に浸水被害をもたらす危険があります。
高潮は満潮時と重なると被害が深刻化するため、沿岸部の住民は気象情報と潮位変化を確認しつつ、早めの避難行動をとることが重要です。そのため、事前に近隣の高台や避難経路を把握しておくことをおすすめします。
津波に関するハザードマップ
津波ハザードマップは、地震による津波の浸水被害を予測した防災地図です。津波ハザードマップには、想定される津波の高さや到達時間、浸水域の範囲が色分けで示されており、海抜や避難場所、避難経路なども詳しく記されています。
津波は第一波より第二波、第三波の方が高くなることも多く、引き波の速さと威力も非常に強いため、沿岸部の住民は「より遠く、より高く」を意識した避難行動をとることが大切です。
土砂災害に関するハザードマップ
土砂災害ハザードマップは、急傾斜地や崖地での崩壊、土石流、地滑りなどの危険区域を示した防災地図です。法律に基づき各市町村が作成する土砂災害ハザードマップには、過去の災害履歴や地質調査の結果から、特別警戒区域(レッドゾーン)や警戒区域(イエローゾーン)が色分けされ、災害の種類ごとに危険度が示されています。
住民は、自宅周辺の危険箇所や安全な避難経路、避難場所を事前に把握できるため、迅速な避難行動につながります。
火山に関するハザードマップ
火山ハザードマップは、火山活動による被害の範囲や種類を予測した防災地図です。特に降灰は風向きによって広範囲に影響を及ぼし、2015年の口永良部島の噴火では、火口から3キロ離れた地域まで火山灰が到達したと言われており、遠方だからと言って被害が無いとは限りません。
火山周辺の住民は、避難所の位置や避難経路に加え、危険な火山ガスの発生が予想される区域なども事前に確認し、いつでも避難できる準備をしておくことが大切です。
宅地に関するハザードマップ
宅地ハザードマップは、谷や沢を埋め立てた造成地や、大規模な盛土による宅地造成地の災害リスクを示した地図です。宅地ハザードマップでは、造成年代や盛土の厚さ、地形の特徴から危険度を評価し、災害時に地滑りや崩壊が起きやすい区域が色分けされています。
引っ越しや住宅購入を検討する際には、このマップで土地の成り立ちや災害リスクを確認し、安全な住まい選びに活用することをおすすめします。
地震危険度に関するハザードマップ
地震に関するハザードマップは、地域ごとの揺れやすさや建物被害、液状化の危険度を予測した防災地図です。地震に関するハザードマップでは、地盤の特性や建物の密集度から予測される震度や被害程度が色分けされており、古い木造住宅が密集する地域や軟弱地盤の場所では特に注意が必要です。
住宅の購入時や建て替えを検討する際には、このマップで地域の地震リスクを確認し、必要に応じて耐震設計や補強工事を検討しましょう。
ハザードマップを確認する方法

自分の住む地域のハザードマップを確認したいと思っても、どこで入手すれば良いのかわからない方も多いのではないでしょうか。実は、インターネットを使った便利な確認方法から、直接市区町村に問い合わせる方法まで、さまざまな入手方法があります。
ここでは、ハザードマップの入手方法を具体的に解説します。
ハザードマップポータルサイトを利用する
国土交通省が運営する「ハザードマップポータルサイト」は、全国の災害リスク情報を確認できるWebサービスです。その他には、「わがまちハザードマップ」では各自治体が作成した防災地図を閲覧でき、「重ねるハザードマップ」では洪水や土砂災害、地震など、さまざまな災害リスクを地図上で重ね合わせて表示することができます。
住所や目印となる施設名で検索すれば、その場所の災害危険度をすぐに確認できるため、不動産購入時の土地選びや、避難計画の作成に役立ちます。また、過去の浸水実績なども確認できるため、より実践的な防災対策を立てることが可能です。
市区町村役場へ問い合わせる
各市区町村の役場では、地域の特性に応じた詳細なハザードマップを無料で提供しています。防災課や危機管理課などの窓口で入手でき、自治体のホームページからダウンロードすることも可能です。
また、担当者に直接相談することで、地域特有の災害リスクや、過去の被災履歴、避難所の詳細な情報なども併せて知ることができるため、より具体的な防災対策を立てやすくなります。
防災アプリを利用する
スマートフォン向けの防災アプリは、災害情報共有システム「Lアラート」と連携し、リアルタイムの災害情報を提供する便利なツールです。特に、Yahoo!防災速報やNHK防災アプリでは、警報や注意報の発令状況、河川の水位情報、気象レーダー画像なども確認できるため、災害時の迅速な避難行動をサポートします。
また、普段から家族との待ち合わせ場所を登録しておけば、いざという時の連絡手段としても活用できます。
不動産情報ライブラリを利用する
国土交通省が運営する「不動産情報ライブラリ」は、土地選びで重要な災害リスク情報を無料で確認できるWebサービスです。不動産情報ライブラリでは、その土地が洪水で浸水する可能性がある区域なのか、津波が到達する恐れはないのかといった情報を地図上で確認できるため、とても便利です。
また、災害時に避難する施設の場所も分かるため、安全な住まい選びの参考になります。このように、不動産情報ライブラリを活用することで、購入を検討している土地の災害リスクを事前に把握できるため、より安心な土地選びにつながるでしょう。
ハザードマップポータルサイトの見方

ハザードマップポータルサイトには「重ねるハザードマップ」と「わがまちハザードマップ」という2つの主要な機能がありますが、初めて利用する方にとっては使い方がわかりにくいかもしれません。特に、地図の見方や災害情報の確認方法など、具体的な操作方法に戸惑う方も多いのです。
ここでは、それぞれの機能の基本的な使い方から、確認できる情報の種類まで、わかりやすく解説します。
重ねるハザードマップの使い方
ハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」では、地域を指定するだけで土地の災害リスクを簡単に確認できます。希望の地域は、地図をクリックするか、住所を入力して指定しましょう。
その後、洪水や地震、土砂災害といった確認したい災害の種類を選べば、リスクの度合いが色分けで地図上に表示されます。さらに、その場所をクリックすると、具体的な被害想定や危険度がわかるため、土地選びの判断材料として役立ちます。
重ねるハザードマップで確認できる情報
「重ねるハザードマップ」は、さまざまな災害リスクを地図上で確認できる便利なツールです。大雨による河川の氾濫時に想定される浸水エリアや浸水の深さ、土砂災害が発生する可能性がある場所、過去に実際に発生した土砂災害の履歴までわかります。
また、台風による高潮被害や地震による津波の想定区域も確認できます。さらに、災害時に通行止めになりやすい道路や冠水の可能性がある場所といった道路防災情報も地図上に表示されるため、土地の災害リスクを具体的に理解できるでしょう。
わがまちハザードマップの使い方
「わがまちハザードマップ」は、市町村が独自に作成した詳細な防災情報を確認できるサービスです。ハザードマップポータルサイトにアクセスし、確認したい地域を選ぶと、その地域で公開されているハザードマップの一覧が表示されます。
「重ねるハザードマップ」と同様の簡単な操作で利用できますが、各自治体が作成しているため、避難所の場所や地域特有の災害リスクなど、よりきめ細かい情報を得ることができます。地域の実情に即した防災情報を知ることで、確実な災害対策を立てられる点が特徴です。
わがまちハザードマップで確認できる情報
「わがまちハザードマップ」では、地域固有の詳細な災害リスク情報を確認できます。河川氾濫による浸水想定区域はもちろん、下水道や水路からの内水氾濫の危険性も把握できます。
また、ため池の位置や決壊時の浸水予測、高潮や津波による被害想定区域も確認しましょう。土砂災害の危険箇所や過去の発生履歴、火山がある地域では噴火による降灰や火砕流の影響範囲まで確認できます。
さらに、地震時の危険度や道路の通行規制予測なども表示されますが、これらの情報は地域の実情に応じて提供されるため、その地域特有の災害リスクに焦点を当てた情報となっています。
ハザードマップで知っておきたい情報

ハザードマップを手に入れても、地図上のさまざまな情報をどのように読み取り、実際の防災に活用すれば良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。災害時に本当に役立つ情報を得るためには、地形の特徴から避難経路まで、複数の要素を総合的に確認することが大切です。
ここでは、ハザードマップから読み取るべき重要な情報と、その活用方法を具体的に解説します。
地形の特徴を把握する
地形は災害リスクと密接に関係しているため、土地選びでは慎重な確認が必要です。ハザードマップを見ると、周囲より低い窪地や谷地形といった水が集まりやすい場所を特定できます。
また、河川近くの低地では氾濫時の浸水深が深くなる傾向があり、海沿いの土地では津波の影響を受けやすいといった特徴もわかります。さらに、傾斜地では土砂災害の危険性が高まるため、周辺の地形との関係性を含めて総合的に判断することが賢明です。
災害の危険性を把握する
ハザードマップは、その土地の災害リスクを視覚的に理解できる貴重な情報源です。地図上には過去に発生した水害や地震、土砂災害といった自然災害の履歴が記録されており、被害の規模や範囲まで細かく確認できます。
過去の災害履歴と予測される被害規模を知ることで、その土地が持つ災害リスクをより具体的に把握できるため、安全な住まい選びの判断材料として役立ちます。
避難先の場所を把握する
ハザードマップには、災害発生時の避難施設の場所が詳しく記載されています。自宅から最寄りの避難所までの距離や経路を確認できるため、実際の災害時にスムーズな避難行動が取れるよう備えられるでしょう。
また、避難所の場所は災害の種類によって異なることがあり、地震の際は学校や公民館、津波の場合は高台の施設、大雨や台風では浸水しない場所の避難所が指定されています。
避難経路を把握する
ハザードマップには避難所が示されていますハザードマップを参考に、避難所までの避難経路に危険な場所はないか、急な坂道や狭い道、橋などの通行が困難になりそうな箇所がないかを把握しておきましょう。
また、主要な避難経路が災害時に通行できなくなる可能性も考慮し、複数の代替ルートを見つけておくことが賢明です。
災害に強い土地選びや家づくりのポイント

ハザードマップで地域の災害リスクを確認したものの、具体的にどのような対策を講じれば良いのか悩む方も多いのではないでしょうか。実は、土地選びの段階から災害リスクを考慮し、適切な対策を施すことで、自然災害に強い住まいを実現することができます。
ここでは、土地の選び方から、耐震性能の高い家づくり、さらには停電対策まで、災害に備えた住まいづくりのポイントを解説します。
土地探しからハウスメーカーに相談する
土地探しの段階からハウスメーカーに相談することは、家づくりを円滑に進めるポイントとなります。土地探しを支援してくれるハウスメーカーでは、地盤の状態や改良工事の必要性まで細かくチェックしながら、災害に強い土地を見つけることができます。
土地と建物をセットで契約すると、安くなることが多く、資金調達の負担が軽減されます。さらに、建築制限を踏まえた上で土地選びができるので、購入後に希望の家が建てられないといったトラブルを防ぐことも可能です。
ハウスメーカー経由の土地購入では仲介手数料が不要になるケースもあり、土地代や建築費用、その他諸経費を含めた総額を明確に把握できるのもメリットの一つとなっています。
地震に強い家づくりができるハウスメーカーに依頼する
建物の耐震性能は、1981年の建築基準法改正を境に大きく向上しています。現行の新耐震基準では、震度6強から7程度の揺れにも耐えられる構造が要求されるため、これから新築する住宅は高い耐震性を備えています。
さらに安心を求めるなら、耐震等級3など、基準以上の性能を持つ住宅を建てることができます。耐震等級とは建築基準法や建築基準法施工令にて定められた建物の耐震性能を表す指標のことで、耐震等級3はその性能が一番高いものになります。各ハウスメーカーは独自の耐震技術や工法を持っているため、実績や対策内容を詳しく確認するのがおすすめです。
ZEH(ゼッチ)住宅で停電対策を検討する
ZEH住宅は、高性能な断熱材や省エネ設備により、光熱費を大幅に抑えることができます。さらに、太陽光発電システムや蓄電池を備えることで、災害時の停電にも対応できる強みがあります。
確かに一般住宅と比べて建築費用は上がりますが、光熱費の削減効果に加え、国の補助金制度も利用できるため、長期的に見ると経済的なメリットがあるのです。また、年間を通じて室温が安定し、真夏や真冬でも快適に過ごせるため、住み心地の面でも大きな魅力があります。
まとめ|ハザードマップの見方を理解して上手に活用しよう

この記事では、ハザードマップの基本的な概要から、さまざまな種類や確認方法まで詳しく解説しました。ハザードマップを確認する方法としては、ハザードマップポータルサイトの利用が便利ですが、市区町村役場への問い合わせや防災アプリの活用など、複数の選択肢があります。
また、地形の特徴や災害の危険性、避難場所や避難経路といった重要な情報も、ハザードマップを通じて把握することができます。これらの情報を土地選びや家づくりに活用することで、より安全な住環境を実現できるでしょう。
特に、地震に強い家づくりやZEH住宅の検討など、災害への備えを考慮した住宅選びも大切です。ハザードマップの見方を正しく理解し、防災・減災に役立てていきましょう。
※この記事で紹介した情報は2024年11月時点のものであるため、最新情報を常に確認しておきましょう。
注文住宅の土地選び・資金計画に
お悩みはありませんか?
「ウチつく」オンライン無料相談なら
プロが徹底サポート!
-
家づくりの準備がワンストップで整う
段取り解説から、1級FPへの個別相談、プロ専用の土地情報検索ツールによるエリア検討まで。
-
住宅メーカーを熟知した住宅のプロに聞ける
専門アドバイザーが中立な立場から、あなたに合った住宅メーカーをご紹介。営業担当者のオーダーも受け付けます。
-
最短1時間・オンラインで気軽に相談できる
スマホでもOK。平日でも土日祝でも、家族の都合に合わせられます。
ハウスメーカーから地域密着型の工務店まで
幅広いラインアップ
ほか、厳選された提携メーカー続々増加中!
参加特典 ウチつくアドバイザーよりご紹介した住宅メーカーが対象


Amazonギフトカード 3,000円分プレゼント!


Amazonギフトカード 50,000円分プレゼント!
納得・安心の家づくりなら
「ウチつく」にお任せください!
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事