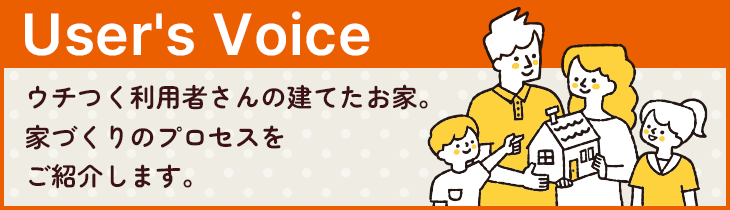年収別のマイホームの購入可能額の目安と住宅ローン以外に注意すべきポイント

マイホームの購入を計画する場合、予算を検討することは大切です。具体的な予算を立てることで、購入できる家が明確になって、購入までの予算の心配をする必要もなくなります。
予算を立てるうえで、自身の年収は1つの基準となる要素です。現在の年収と照らし合わせて、規模や設備の充実度など、購入できる家を判断することができます。また、住宅ローンを利用する場合の月々の返済額など、購入費以外にも金銭面で気になる点は多いと思います。
今回は、年収別でのマイホーム購入額の目安や、住宅ローン以外に注意しなければいけないポイントを解説します。多くの方にとって理想とも言えるマイホームの購入において、金銭面における不安を抱える方はいると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
年収別のマイホーム購入可能額の目安を住宅ローンの借入可能額で比較
フラット35の借入可能額シミュレーション(融資金利1.8%、返済期間35年、元利均等として計算)を参考に解説します。
| 世帯年収 | 借入可能額 |
| 200万円~400万円 | 約1,500万円~約3,600万円 |
| 500万円 | 約4,500万円 |
| 600万円 | 約5,400万円 |
| 700万円 | 約6,300万円 |
| 800万円以上 | 約7,200万円~ |
マイホームを購入する方の平均年収と平均費用
マイホームを購入する方の平均年収は624万円
マイホームとして注文住宅を建てる場合、年収は624万円程度あるのが目安になります。
ただし、年収が624万円より少ないからといって購入できないということはなく、予算計画や返済計画、年収アップなどによって購入することもできます。
マイホーム購入にかかる平均費用は3,935万円
国土交通省の調査によると、マイホームを購入するのに必要な費用の平均は、3,935万円となっています。
住宅ローンを組むと、購入金額以上に負担の金額が大きくなります。仮に住宅ローンで3,935万円を借り入れ、元利均等で35年間、固定金利1.8%で返済すると総返済額は53,066,569円となります。毎月の返済額は、128,436円です。
マイホームの購入費用ではなくて、住宅ローンの毎月の返済金額を計算して生活の負担になるかならないかを判断しましょう。
マイホーム購入の住宅ローン利用者は年収400万円~800万円の方が多い
マイホームを手に入れるために住宅ローンを利用する方のうち、固定期間選択型、全期間固定型は年収が400万円以上800万円以下という方が多いという調査結果が住宅金融支援機構が行った「住宅ローン利用者の実態調査」で報告されています。
年収400万円以上800万円以下という数値は、住宅ローンを利用してマイホームを購入するときの年収の目安になります。
マイホーム購入費用の相場と返済負担率
マイホームの購入費用の相場は年収の約6~7倍が相場
マイホームの購入費用については、年収の約6~7倍が目安となっています。
2022年度フラット35利用者調査によると、世帯平均年収が634万円となっています。たとえば年収が600万円の場合、3,600万円~4,200万円が購入費用として必要になると想定します。購入費用に上限はありませんが、年収に対して高額な費用のかかる家を買ってしまうと、購入後の維持費や借り入れた住宅ローンの返済が負担になってしまう可能性があります。
年収に見合ったマイホームを建てて、返済負担を大きくしすぎないためにも、年収の6~7倍の住宅をマイホームとして建てるようにしましょう。
マイホーム購入の際は返済負担率を手取り年収の20~25%で納める
マイホームを購入するときの1つの目安になるのが、返済負担率です。返済負担率とは、年間の返済額が年収の何パーセントになるかを示した割合を指します。
たとえば年収500万円で、年間の返済額が100万円だとすると、返済負担率は100÷500=0.2となり、20%ということになります。返済負担率によって、毎年の返済による負担を具体的に数値化することができます。
返済負担率については、20%~25%程度が、負担を抑えつつ返済がおこなえる目安です。25%を超えてしまうと、住宅ローン以外に発生する出費に備えられなくなる可能性があります。子どもの進学や事故、病気といった場面でお金を用意するのがむずかしくなり、生活を圧迫しかねません。
マイホーム購入で年収以外に注意すべきポイント
購入する家の1~2割程度の頭金を用意
平均給与が上がらないなどの理由から頭金の額は減りつつある
住宅ローンの負担を減らす方法として、頭金を用意するというものがありましたが、近年では頭金を用意する方や金額が減っているという現象が起きています。
頭金を準備しない理由として大きいのは、平均給与の伸びが鈍いことです。給与が増えないことで頭金としての資金を貯蓄できず、頭金を用意するのに時間がかかってしまうという問題があります。
住宅ローン以外の諸費用を用意
マイホームを建てるうえで、住宅ローン以外にも諸費用がかかるので資金を用意しておく必要があります。
諸費用には仲介手数料や手続きにかかる手数料、保険料などが含まれています。諸費用はマイホームを購入すると付随してくる費用で、支払わなければマイホームを建てることはできません。新築のマイホームを建てる場合、家の価格の約3%から7%、一方で中古物件を買う場合は約6%から13%が諸費用として必要になると想定されます。
上記の割合を目安に、諸費用を準備しましょう。また、諸費用は現金での支払いが求められるものもあるので、現金で用意しておくことも欠かさずにおこないましょう。
マイホームを購入したいが年収が足りない場合
親から援助を受けられないか相談する
もし年収が足りなくてマイホームが建てられないと感じたときは、親からの援助を受けられないか相談してみましょう。
親や祖父母からの援助された資金は、贈与税が非課税になって受け取ることができる場合があります。援助を受けられれば返済負担を減らすことができますが、援助金が非課税となる特例を受けるには一定の条件を満たさなければいけないので、注意が必要です。
賃貸併用住宅で家賃収入を得る
年収の足りない分を補う方法として、賃貸併用住宅を建てるというのがあります。
賃貸併用住宅とは、住宅の一部を自分で住む空間に、残りを賃貸住宅に住みたいという方に貸す空間を併用する住居を指します。賃貸併用住宅を利用することで、マイホームに住みつつ家賃収入を得られるので、住宅ローンの返済負担を抑えることができます。
ただし、マイホームに他人が住むことを心地よく思わない場合は控えましょう。また、賃貸専用の部屋が空室になってしまった場合家賃収入が得られないので、返済が滞ってしまうリスクもあります。
フラット35を利用して購入する
フラット35の住宅ローンは年収による借入額などの制限がないため、年収が足りないという課題を解決できます。
フラット35では住宅金融支援機構が住宅ローンを提供していて、固定金利という特徴があります。利点としては、保証人の必要がないことや保険への加入が任意であることが挙げられます。
建売住宅や中古物件などより安い物件も選択肢に入れて探す
マイホームを建てるための資金が足りないと感じたら、新築物件だけを探すのではなく、建売住宅や中古物件などを検討する方法もあります。
建売や中古の物件は手ごろな価格のものが多く、新築住宅とくらべて購入のハードルが低いです。また、中古物件であれば自分の好みに合わせて家を改装することもできるので、自由度で見れば中古物件を選ぶ方が良いです。
広く探せば、新築住宅と同じ間取りでありながら格安で購入できる、ということもあります。資金に不安がある場合は、中古物件も探してみましょう。
RANKING
ランキング
PICK UP
おすすめ記事